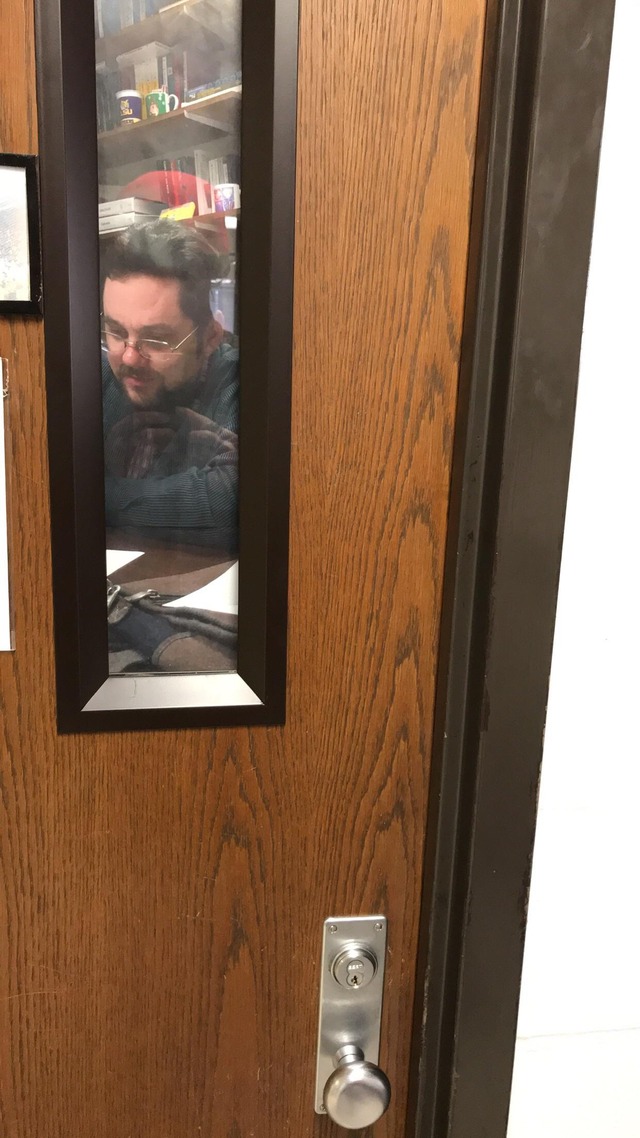Comment by zeppelin22※なるべく未訳のものは除き、日本語訳があるものを中心に載せています。
君達のお勧めのノンフィクション書籍って何?
reddit.com/r/AskReddit/comments/71yni4/what_is_your_favorite_nonfiction_book/
reddit.com/r/AskReddit/comments/7dtkqm/what_nonfiction_books_do_you_think_everyone/
reddit.com/r/AskReddit/comments/7q5icl/what_nonfiction_books_do_you_recommend/
reddit.com/r/AskReddit/comments/1ty5au/what_is_the_most_interesting_nonfiction_book/
reddit.com/r/AskReddit/comments/20eguy/which_nonfiction_book_alsolutely_blew_your_mind/
reddit.com/r/AskReddit/comments/1hoxfa/what_nonfiction_books_should_everyone_read_to/
reddit.com/r/books/comments/10g5xb/what_is_the_best_non_fiction_book_you_have_ever/
関連記事
外国人「絶対見た方が良いドキュメンタリーを紹介していく」海外のまとめ
「外国人がお気に入りの『ディストピア小説』を紹介していくスレ」海外のまとめ
外国人「文章力のある歴史家が書いたお勧めの著作を教えてほしい」海外のまとめ
Comment by writetheotherway 229 ポイント
オリバー・サックスの「妻を帽子とまちがえた男」
これは事例調査を収集したものだけどなかなか興味深い。
あとデイビット・シェンクの「天才を考察する―「生まれか育ちか」論の嘘と本当」。
Comment by Lenwey 1 ポイント
↑気になったんだけどそれって人の状態に関する心理学?
Comment by [deleted] 2 ポイント
↑興味深い精神病患者たちの事例調査がいくつか載ってる。
タイトルの話はその30話(くらい)の中の一つ。
妻の頭を帽子とまちがえてかぶろうとする音楽家、からだの感覚を失って姿勢が保てなくなってしまった若い母親@@脳神経科医のサックス博士が出会った奇妙でふしぎな症状を抱える患者たちは、その障害にもかかわらず、人間として精いっぱいに生きていく。そんな患者たちの豊かな世界を愛情こめて描きあげた、24篇の驚きと感動の医学エッセイの傑作、待望の文庫化。アインシュタインら歴代の天才を対象に行なわれた「天才研究」から最新の遺伝子・ゲノム理論、発達心理学の成果までを簡潔かつわかりやすく紹介しながら、古い論争がいかにナンセンスであったかを説く、出色のポピュラー・サイエンス。
Comment by ElolvastamEzt 200 ポイント
「ご冗談でしょう、ファインマンさん」は面白かった。
http://www.amazon.com/Surely-Feynman-Adventures-Curious-Character/dp/0393316041
これは物理学者リチャード・ファインマンの回顧録。読んでてすごく面白い。
Comment by lridescent 9 ポイント
↑この本ってどのスレッドでも取り上げられるよね。
ファイマンは個人的な英雄でもあるし、20世紀最高の知性。あとこの本では何が彼を彼たらしめたのかについての考察もある。
Comment by horacetheclown 3 ポイント
↑彼はこれを回顧録と呼ばれるのは嫌がってたけどね。逸話集と呼ばれる方を好んでた。
Comment by mind_in_space 2 ポイント
↑「聞かせてよ,ファインマンさん」のことも忘れないように!!
少年時代より変わらぬ,あくなき探求心といたずらっ気….20世紀を代表する物理学者が,奇想天外な話題に満ちた自らの人生をユーモアたっぷりに語る.ノーベル賞受賞をめぐる顛末,また初来日の時の“こだわり”など,愉快なエピソードのなかに,とらわれぬ発想と科学への真摯な情熱を伝える好読物.もしもファインマンさんの講演会があったなら、今だって会場には溢れんばかりの人がおしかけるだろう。学問のいかめしさとは全く無縁、不思議を突き止めていく科学のワクワク、ドキドキを、抱腹絶倒の語り口で伝えてくれるから。そんなファインマンさんの、講演・インタビューをまとめた一冊。話題は生い立ちから、素粒子や宇宙の話まで。
Comment by Bic823 176 ポイント
ジョン・クラカウアーの作品はマジで良い。
個人的には「荒野へ」と「信仰が人を殺すとき - 過激な宗教は何を生み出してきたのか」が良かった。
Comment by wizzo89 9 ポイント
↑「Where Men Win Glory」も秀作。読んだことがないなら読んでみるべき。たとえパット・ティルマンの事を知らなくても。
アラスカの荒野にひとり足を踏み入れた青年。そして四か月後、うち捨てられたバスの中で死体となって発見される。その死は、やがてアメリカ中を震撼させることとなった。恵まれた境遇で育った彼は、なぜ家を捨て、荒野の世界に魅入られていったのか。登山家でもある著者は、綿密な取材をもとに青年の心の軌跡を辿っていく。全米ベストセラー・ノンフィクション。「彼らを殺せ」と神が命じた―信仰とはなにか?真理とはなにか?一九八四年七月、米ユタ州のアメリカン・フォークで二十四歳の女性とその幼い娘が惨殺された。犯人は女性の義兄、ロナルド・ラファティとダン・ラファティであった。事件の背景にひそむのは宗教の闇。パトリック・ダニエル・ティルマン(Patrick Daniel "Pat" Tillman 1976年11月6日 - 2004年4月22日)はカリフォルニア州フリーモント出身のアメリカンフットボール選手。NFLのアリゾナ・カージナルスに在籍していたが2001年に起きたアメリカ同時多発テロ事件をきっかけに2002年5月、アメリカ陸軍に志願しレンジャー部隊に入隊した。アフガニスタンに派遣された彼は2004年4月22日、友軍の誤射で死亡した。当初彼の亡くなった経緯は隠されテロとの戦争における英雄扱いがなされた。
Comment by sheeku 315 ポイント
ジョン・クラカワーの「空へ―エヴェレストの悲劇はなぜ起きたか」
この本は1996年にエベレストで11人が死亡した悲劇についての個人記録。
このアクシデントはヒューマンエラー、うぬぼれ、競争によって引き起こされた。何度読んでも飽きない。
Comment by cizzlewizzle 29 ポイント
↑アナトリ・ブクレーエフの「デス・ゾーン8848M―エヴェレスト大量遭難の真実」も読む価値がある。
これはその悲劇を別の視点から見ることが出来る。
Comment by slvrbullet87 16 ポイント
↑エベレストで人が死ぬ話を読んだらどういうわけかエベレストに登りたくなった。
’96年5月、多くの死者を出したエヴェレスト登山隊に参加、九死に一生をえて生還した作家が描くエヴェレスト大量遭難の軌跡。1996年5月10日、エヴェレスト南東稜、海抜八千メートルを超える死の領域で発生した未曽有の大量遭難事故。多数の命を奪った空白の数時間にいったい何があったのか。驚くべき真実を伝えるドキュメント。
Comment by poomcgoo8 131 ポイント
ダグラス・ホフスタッターによる「ゲーデル、エッシャー、バッハ―あるいは不思議の環」
論理学の基礎に関する分析。これを読んで知的に。
Comment by DoWhile 2 ポイント
↑ホフスタッターの法則:いつでも予測以上の時間がかかるものである、ホフスタッターの法則を計算に入れても。
『ゲーデル、エッシャー、バッハ - あるいは不思議の環』(ダグラス・ホフスタッター著、野崎昭弘、はやしはじめ、柳瀬尚紀 訳、原題は Godel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid)は、1979年に米国で刊行された一般向けの科学書。
1985年に白揚社から日本語訳が発行され、1980年代後半から90年代前半にかけて日本でも小ブームが起きた。
ゲーデル、エッシャー、バッハ
『ゲーデル、エッシャー、バッハ』において、ホフスタッターはよく引用されることになるホフスタッターの法則を書いている。次の通りであるが、自己言及を含んでいることが特徴と言えよう:
いつでも予測以上の時間がかかるものである — ホフスタッターの法則を計算に入れても。
ホフスタッターの法則
Comment by triplesalmon 121 ポイント
カール・セーガンの「カール・セーガン 科学と悪霊を語る」
僕は昔は新世界秩序とか国家陰謀論とか霊能力とか言ったものを信じていたけどこの本を読んで懐疑的になってそれから一顧だにしないようになった。
この本でかなり理性的な人間になった。強くお勧めする。
Comment by navyjeff 16 ポイント
↑この本は目から鱗だった。友人や親戚みんなに勧めたけど実際に読んだのはほんの僅か。
超能力、火星人、心霊術…人はなぜエセ科学に騙されるのか。ロズウェル事件やカルロス事件など数々の実例を挙げ、エセ科学の「闇」を徹底的に撃つ。惜しくも亡くなった宇宙物理学者による長編科学エッセイ。
新世界秩序(しんせかいちつじょ、New World Order、略称:NWO)とは、国際政治学の用語としては、ポスト冷戦体制の国際秩序を指す。また陰謀論として、将来的に現在の主権独立国家体制を取り替えるとされている、世界政府のパワーエリートをトップとする、地球レベルでの政治、経済、金融、社会政策の統一、究極的には末端の個人レベルでの思想や行動の統制・統御を目的とする管理社会の実現を指すものとしても使われる。
新世界秩序
Comment by guts_full_of_meat 110 ポイント
「天才! 成功する人々の法則(Outliers)」
成功者とその成功が何によるのかについての話を興味深く読める。
Comment by Accidentus 54 ポイント
↑要約;幸運と勤勉。
Comment by adrianjaworski 13 ポイント
↑グラッドウェルの「逆転! 強敵や逆境に勝てる秘密(David and Goliath)」も忘れないように。
個人的には「天才! 成功する人々の法則」と同じ位には良書だと思う。
持つ者はさらに豊かになり、持たざる者はもっているものを取り上げられる「マタイ効果」。どんな才能や技量も、一万時間練習を続ければ“本物”になる「一万時間の法則」…グラッドウェルのフレームワークはやっぱり面白い。
Comment by soxfan17 108 ポイント
ローラ・ヒレンブランドの「不屈の男 アンブロークン」
一人の人間がここまで出来るのかと思うと感嘆する。
米国代表ランナーとして五輪に出場したルイは、第二次大戦時、B-24の墜落で太平洋を47日間漂流する。奇跡的に到着した島には日本軍が。彼は捕虜として日本に送られ、想像を超えた過酷な生活を強いられる。
Comment by SlayerChartzilla 370 ポイント
「ヤバい経済学: 悪ガキ教授が世の裏側を探検する」
経済と現実世界についての「猿でも分かる入門書」
この本で取り上げてる話題についてそれまで全然知らなかったし関心もなかったけど今では関心持ってる。それになかなか滑稽。
お勧め!
Comment by _Doctor_Teeth_ 72 ポイント
↑他の秀逸な経済学入門書としては「Naked Economics: Undressing the Dismal Science.」がある。
「ヤバい経済学: 悪ガキ教授が世の裏側を探検する」ほど興味深いものではないけど、経済の概念や経済の機能についてはこっちの方がきちんと説明してる。
「ヤバい経済学: 悪ガキ教授が世の裏側を探検する」はどっちかというと経済観点から見た逸話集でミクロ経済、行動経済寄り。
そっちの方が読み物としては楽しめたけど「Naked Economics」の方がより多くの事を学べた気がする。
銃とプール、危ないのはどっち?相撲の力士は八百長なんてしない?学校の先生はインチキなんてしない?ヤクの売人がママと住んでるのはなぜ?出会い系サイトの自己紹介はウソ?若手経済学者のホープが、日常生活から裏社会まで、ユニークな分析で通念をひっくり返します。アメリカに経済学ブームを巻き起こした新しい経済学の書、待望の翻訳。私たちは絶え間なく経済に関わっています。毎日の仕事も経済活動のうちのひとつですし、スーパーやコンビニなどでの買い物も、まぎれもない経済活動です。現代の日本に住んでいて、経済とまったく関わらないという人はおそらく誰一人としていないでしょうか。
ところが私たちの多くは、この毎日深く関わっている「経済」というものを案外よく知りません。この本はこの「経済」というものが身近でわかりやすく面白いものだ、ということに気づかせてくれる本です。チャートやグラフなどは全く使わず、経済の素人が直感的にわかる内容になっています。
Comment by iamnotstrappedin 170 ポイント
レベッカ・スクルートの「不死細胞ヒーラ: ヘンリエッタ・ラックスの永遠なる人生」
彼女の名はヘンリエッタ・ラックス。だが、科学者には「ヒーラ」として知られている。1951年、貧しい黒人のタバコ農婦だった彼女の身体から、本人の同意なく採取された癌細胞は、のちに医学界のきわめて重要なツールとなる。それはポリオワクチンの開発、クローニング、遺伝子マップの作製をはじめ、幾多の研究の礎となった。しかし数十億個という膨大な単位でその細胞は売買されてきたにもかかわらず、ヘンリエッタは死後も無名のままにとどまり、彼女の子孫もまた健康保険すらまかなえない境遇に置かれていた―。
倫理・人種・医学上の争い・科学的発見と信仰療法、そして、亡き母への想いと葛藤に苦悩する娘の物語を鮮やかに描いた『ニューヨーク・タイムズ』ベストセラー。
Comment by Anastik 163 ポイント
ヴィクトール・フランクルの「夜と霧」
強制収容所での経験が書かれたもので、自分たちの幸福をどうコントロールするかについての興味深い考えが示されてる。
困難な状況で苦しい時にはこの本にかなり助けられてる。
Comment by pennyinpurple 4 ポイント
↑人格理論の講義で読んだけどお勧め。
ユダヤ人精神分析学者がみずからのナチス強制収容所体験をつづった本書は、わが国でも1956年の初版以来、すでに古典として読みつがれている。著者は悪名高いアウシュビッツとその支所に収容されるが、想像も及ばぬ苛酷な環境を生き抜き、ついに解放される。家族は収容所で命を落とし、たった1人残されての生還だったという。
このような経験は、残念ながらあの時代と地域ではけっして珍しいものではない。収容所の体験記も、大戦後には数多く発表されている。その中にあって、なぜ本書が半世紀以上を経て、なお生命を保っているのだろうか。今回はじめて手にした読者は、深い詠嘆とともにその理由を感得するはずである。
Comment by SayMyName2 73 ポイント
ジャネット・ウォールズの「ガラスの城の子どもたち」
自分の体が炎に包まれていた。それが私の最初の記憶だ――育児放棄(ネグレクト)に負けず、強く生きた著者が語る感動のメモアール。YAに読ませたい本を選ぶアレックス賞受賞。
ガラスの城の子どもたち
Comment by torbjorg 146 ポイント
トーマス・クーンの「科学革命の構造」
これで人生変わったし世界の見方も変わった。
Comment by probablyanorange 4 ポイント
↑これ哲学の講義の導入に読んだ。興味深いってことには同意するけど結構批判があるんじゃなかったっけ?
Comment by demolitionsquid 5 ポイント
↑そうそう。科学哲学の講義を受講したけどその教授は「科学革命の構造」は影響力があったけど大半を単純化し過ぎてるって言ってた。
科学における進歩とは何か。世界観の変革は、いかにして起るか。
本書は「パラダイム」概念を武器として、未開拓のテーマたる「科学革命」を鋭く分析し、
コペルニクスからボーアまでの科学の歴史に新しい展望を与える。
Comment by lenseraGeneral Fiction 173 ポイント
ジャレド・ダイアモンドの「銃・病原菌・鉄」と「文明崩壊: 滅亡と存続の命運を分けるもの」を読んだけど非常に興味深かった。
「銃・病原菌・鉄」
http://www.amazon.com/Guns-Germs-Steel-Fates-Societies/dp/0393061310/
「文明崩壊: 滅亡と存続の命運を分けるもの」
http://www.amazon.com/Collapse-Societies-Succeed-Revised-Edition/dp/0143117009/
Comment by animalzhu 7 ポイント
↑それが有益な本であるということには同意するけどジャレド・ダイアモンドの出してるデータは他の人から反証されていたり違う解釈をされているものが多いから、彼の結論は実際に起きた出来事に沿っていない可能性がある。
Comment by crabpeople69 2 ポイント
↑確かに。大学の一般教養の講義で読んだことがある。
それとは別に「「強国」論: 富と覇権の世界史」も読んだ。その時の議論は今でも心に残ってる。
Comment by Rene_Locker 1 ポイント
↑それ関連だと、イアン・モリスの「人類5万年文明の興亡: なぜ西洋が世界を支配しているのか」をお勧めする。
「銃・病原菌・鉄」と似たような疑問を多々扱っているけど切り口が違ってる。
あと結論(近未来について)は結構驚き。ネタバレしたくないから詳しくは本を読んでもらえればと思うけど、結論だけを目当てに読む価値はあるよ。
これを読むならレビューやネタバレは先に読まない方が良い。
なぜ人類は五つの大陸で異なる発展をとげたのか。分子生物学から言語学に至るまでの最新の知見を編み上げて人類史の壮大な謎に挑む。ピュリッツァー賞受賞作。識者が選ぶ朝日新聞“ゼロ年代の50冊”(2000年から2009年の10年間に出版された本)堂々の第1位に選ばれた名著中の名著、遂に文庫化。イースター島やマヤ文明など、消えた文明が辿った運命とは。繁栄が環境に与える負荷の恐るべき結末を歴史的事例で検証し文明存続の道を探る。全米ベストセラー。博識に裏付けられた歴史的観点を通して、「勝者」と「敗者」を分けたものは何だったのかを探り、人類が歩んできた経済発展という壮大なドラマを総括する。1842年、イギリスが阿片戦争に勝利して以来150年間、西洋は紛れもなく東洋を圧倒し、世界を支配している。だが、なぜ歴史はそのように展開したのか。それは歴史の必然なのか、あるいは単なる技術革新の勝利なのか。それとも西洋には本質的に何かしら有利な条件があったのか。西洋と東洋、それぞれの文明を人類の黎明期からたどり直してみると、いずれにおいても似たような発展と衰退のパターンをくり返してきたのがわかる。過去のあらゆる文明を行き詰まらせた5つの要因とは何か―。スタンフォードの歴史学教授が圧倒的なスケールで人類史を俯瞰、現在の文明世界の閉塞状況をクリアに描き出す。
Comment by jimmiesimpsonsmole 15 ポイント
「Blood, Sweat, and Pixel」
どのようにしてゲームが制作されるかについて書かれた良書。
Comment by Dat_Boi_Frog_Memer 40 ポイント
マルクス・アウレリウス・アントニヌスの「自省録」
Comment by TheRealRobertRogers 2 ポイント
↑同じく。人生についての教訓を与えてくれる良書。
著者はローマ皇帝で哲人。蕃族の侵入や叛乱の平定のために東奔西走したが、僅かに得た孤独の時間に自らを省み、日々の行動を点検し、ストアの教えによって新たなる力を得た。静かな瞑想のもとに記された、著者の激しい人間性への追求。
Comment by hufflepuffwhore 28 ポイント
犯罪ドキュメンタリーに興味がある人にはロバート・グレイスミスの「ゾディアック」
僕はこの本を森の中にある小屋で読んでしまうというミスをしてしまった。
読んでる間ずっと凍り付いてたわ。彼は凄い作家。
60年代後半、全米を恐怖におとしいれた連続殺人鬼がいる―その名はゾディアック。殺害方法の残忍さと多様さもさることながら、暗号を使った犯行声明をマスコミ宛に次々と送りつづけてくる犯人の前代未聞の異常さが、人びとを震えあがられた。いまだ解決されていないこの事件にとり憑かれ、みずからの生活を犠牲にしてまで犯人の正体を暴くことに命を賭けた男たちや、凶行の犠牲となった被害者とその家族たち…著者の執念の追跡によって集められた数々の証言と証拠品によって明かされる、稀代の殺人鬼、ゾディアックの全貌!
Comment by isebloodfoolheart 22 ポイント
ジェイムズ・ヘリオットの「ヘリオット先生奮戦記」
気楽に読める本でシリーズ全部が素晴らしい。
厳密に言えばこれは100%ノンフィクションってわけじゃないけど獣医としてちゃんと経験がある人物による作品だから。
著者名はペン・ネームだが、実在の獣医による体験談を小説にしたものだ。
1916年にスコットランドのグラスゴーに生まれ育ってそこの獣医大学を卒業し、獣医助手を募集する広告を見て、1937年にノースヨークシャーの山間部にやってきた。
短気だけれど人のよい獣医、シーグフリード・ファーノン先生と、その弟で頭がよいのに怠け者のトリスタンと『私』の3人の、珍妙な暮しが始まる。
頑固だけれど優しい村の人たち、個性に満ちた動物たち、そしてイギリスの田舎の美しい自然に囲まれて。
獣医の仕事を始めるとすぐ、大学の教科書にはまったく書かれていなかった汚れ仕事、不測の事態、厳しい自然に直面して、『私』の心に後悔がよぎる。
しかし動物や村人たちとの心の交流や往診の行き帰りの自然の豊かさに触れて、『私』は次第にその仕事の素晴らしさに目覚めてゆく。
ヘリオット先生奮戦記
Comment by TriviaWhiz 14 ポイント
マイケル・ルイスの「かくて行動経済学は生まれり」
行動経済学の先駆者であるエイモス・トベルスキーとダニエル・カーネマンに着目した本。
Comment by apyz 6 ポイント
↑それってその人たちの功績について?それとも関係性?それ以外?
「ファスト&スロー」読んだけど面白かった。
Comment by TriviaWhiz 2 ポイント
↑どれも入ってる感じ。彼らの功績やら互いの関係やら彼ら個人の生涯について。
データ分析を武器に、貧乏球団を常勝軍団に作り変えた
オークランド・アスレチックスGMを描いた『マネー・ボール』は、
スポーツ界やビジネス界に「データ革命」を巻き起こした。
刊行後、同書には数多くの反響が寄せられたが、
その中である1つの批判的な書評が著者の目に止まった。
「専門家の判断がなぜ彼らの頭の中で歪められてしまうのか。
それは何年も前に2人の心理学者によって既に説明されている。
それをこの著者は知らないのか」
この指摘に衝撃を受けたマイケル・ルイスは、
その2人のユダヤ人心理学者、ダニエル・カーネマンと
エイモス・トヴェルスキーの足跡を追いはじめた――。
整理整頓好きの青年が図書館司書である確率は高い? 30ドルを確実にもらうか、80%の確率で45ドルの方がよいか? はたしてあなたは合理的に正しい判断を行なっているか、本書の設問はそれを意識するきっかけとなる。人が判断エラーに陥るパターンや理由を、行動経済学・認知心理学的実験で徹底解明。心理学者にしてノーベル経済学賞受賞の著者が、幸福の感じ方から投資家・起業家の心理までわかりやすく伝える。
エイモス・トベルスキー(Amos Tversky、1937年3月16日 - 1996年6月2日)は、心理学者。
プリンストン大学のダニエル・カーネマンらと共同で研究を行い、認知科学を発展させた。カーネマン(2002年ノーベル経済学賞受賞)によると、トベルスキーが生きていれば当然同時に受賞することになったはずである。
エイモス・トベルスキー
ダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman、1934年3月5日 - )は、経済学と認知科学を統合した行動ファイナンス理論及びプロスペクト理論で有名なアメリカ合衆国(ユダヤ人)の心理学者、行動経済学者。
ダニエル・カーネマン
Comment by TwuntyMcWalloper 19 ポイント
リチャード・ドーキンスの「利己的遺伝子」
ドーキンスは反有神論者として悪名高いけど彼はこの時代における傑出した生物学者の一人だよ。
一般的な人が進化の過程について理解してないことにはマジかよってなる。
「なぜ世の中から争いがなくならないのか」「なぜ男は浮気をするのか」―本書は、動物や人間社会でみられる親子の対立と保護、雌雄の争い、攻撃やなわばり行動などが、なぜ進化したかを説き明かす。この謎解きに当り、著者は、視点を個体から遺伝子に移し、自らのコピーを増やそうとする遺伝子の利己性から快刀乱麻、明快な解答を与える。
Comment by gofatwya 15 ポイント
カール・セーガンの「サイエンス・アドベンチャー」
Comment by marsglow 1 ポイント
↑これは良書。あと「人間の測りまちがい―差別の科学史」も。
地球という惑星に生命が誕生してから四十億年に及ぶ生命の全歴史、人類という“家族”が誕生してから四百万年に及ぶ全人類史の中で、ただひとつの世代だけが唯一無二の転換期に生きるという特権を与えられている。人間とは何か、宇宙とは何か?正確な科学知識と多様な話題で、人類と科学の未来を促える。
人種、階級、性別などによる社会的差別を自然の反映とみなす「生物学的決定論」の論拠を、歴史的展望をふまえつつ全面的に批判したグールド渾身の力作にして主著。知能を数量として測ることで、個人や集団の価値を表すという主張はなぜ生まれたのか。差別の根源と科学のあり方を根底から問いかえすための必読の古典。
Comment by shamalongadingdong 73 ポイント
「レオポルド王の霊」
コンゴでヨーロッパ人が犯した蛮行について書かれた本。
ためになるしゾッとする。
『レオポルド王の霊』(King Leopold's Ghost、レオポルド王の亡霊、レオポルド王の幽霊)は、1998年にアメリカ合衆国で出版された、作家アダム・ホックシールドの著作。
1885年から1908年にかけて、ベルギー王レオポルド2世の私領地コンゴ自由国(現・コンゴ民主共和国)で行われた搾取と開発を描く。
レオポルド王の霊
Comment by profanusmaximus 553 ポイント
ビル・ブライソンの「人類が知っていることすべての短い歴史」
単に僕たちが知っていることについてだけじゃなくて、何故それを僕たちが知っているかについての機知にとんだ考察がある。
Comment by cassiope 102 ポイント
↑「ビル・ブライソンの究極のアウトドア体験 北米アパラチア自然歩道を行く」も良い。
今旦那が読んでるけどそのうち私も読んでみる。
宇宙のはじまり、DNA、プレートテクトニクス、10-43秒という時間の長さ。テストのために丸暗記しただけの用語や数字の奥には、驚くべき物語が隠されていた。科学と無縁だったベストセラー作家が一大奮起し、三年かけて多数の専門家に取材、世界の成り立ちの解明に挑む。科学を退屈から救い出した大傑作。アパラチア自然歩道は、アメリカ東部のジョージア州からメイン州まで3500キロに渡る、連続した自然歩道としては世界最長のものである。途中、グレート・スモーキー・マウンテンズ、シェナンドア国立公園などアメリカ有数の景勝地を通るが、その険しさゆえに全行程を踏破する人間は年間300人に満たない。勇躍して出発したブライソンと、モーテルでX‐ファイルを見るのが唯一の楽しみというカッツの前途に待ちうけていたものは…。
Comment by dustlesswalnut 161 ポイント
「悪魔と博覧会」は凄く良かった。
Comment by [deleted] 30 ポイント
↑エリック・ラーソンなら「第三帝国の愛人――ヒトラーと対峙したアメリカ大使一家」も良い。
Comment by Rene_Locker 7 ポイント
↑僕はそれ途中で読むの止めたわ。
なんか興味が持てなかった。多分この本はアメリカ人向けだと思う。
医師の名はH.H.ホームズ。英国の“切り裂きジャック”と踵を接してアメリカに現れた連続殺人犯。一人の刑事が足跡を追って全米を巡り、ついにその仮面を剥ぐ。世界博覧会の栄光と異様な犯罪の対照を描く重量級ノンフィクション。それは始まりに過ぎなかった――。ナチス政権下となって初めての駐独アメリカ大使としてドイツに赴任したドッド一家。まばゆい陽光の公園、美しい青年将校たち、街の煌めく不夜城、フォードでのドライブ、そして、血まみれの生贄。ナチス台頭期ベルリンで一家が遭遇した稀有な体験を、スリリングに描き出した戦慄のノンフィクション。
Comment by Jews-R-Us 123 ポイント
「ラップという現象」
デイヴィッド・フォスター・ウォーレスによるエッセー集。非常に良い。
Comment by AnnaLemma 51 ポイント
↑「Consider the Lobster」もなかなか啓発的だった。
80年代後半の「ラップ/ヒップホップ」文化の黄金期を起点にして、その音楽の意味とアメリカの都市における「黒人」の現在を探る白眉の論考。
Comment by zodiacsnake 74 ポイント
リチャード・プレストンの「ホット・ゾーン 「エボラ出血熱」制圧に命を懸けた人々」は面白かった。
スリル小説みたいな感じに読んでたけど、これが実際に起こったことなんだってことに思い至ると背筋がゾクッとする。
Comment by glemnar 3 ポイント
↑確かに。学校じゃタイトルのせいで周りから笑われるけど。
脅威の感染メカニズムから、ウィルス制圧に命をかけた医療関係者たちの戦いまで――。「エボラ出血熱」のすべてを描ききった、傑作ノンフィクション。
Comment by BisousCherie 55 ポイント
スーザン・ケインの「内向型人間の時代: 社会を変える静かな人の力」
これは秀逸。特に自分の事を内向的な人間だと思っている人にとっては。
Comment by seventeenseconds 3 ポイント
↑他にも内向的な人向けの傑作と言えばマルティ・オルセン・ラニーの「The Introvert Advantage: How to Thrive in an Extrovert World」
Comment by BisousCherie 2 ポイント
↑これ読んだことないからすぐチェックしてみる!
内向型の人とは、喋るよりも他人の話を聞き、パーティで騒ぐよりも一人で読書をし、自分を誇示するよりも研究にいそしむことを好む人のことだ。アメリカ人と言えば、社交的で自己主張が激しそうなイメージがあるが、実際にはその三分の一が内気でシャイな内向型だという。これはアメリカに限ったことではない。
外向型が重視されるアメリカにおいては、内向型の存在感は薄く、出世競争でも不利になりがちだ。本書は、内向型が直面する数々の問題を浮き彫りにするとともに、あまり顧みられることのない内向型の強みと魅力を明らかにし、その個性を伸ばして生かす方法を模索する。
Comment by [deleted] 29 ポイント
バーバラ・デミックの「密閉国家に生きる―私たちが愛して憎んだ北朝鮮」
http://www.goodreads.com/book/show/6178648-nothing-to-envy
Comment by kuffara 12 ポイント
↑似たような作品として「北朝鮮14号管理所からの脱出」も加えたい。
世界は、かの国の“普通の人々”のことを、何一つ知らなかった―一〇〇人以上の脱北者に取材を重ねてきたアメリカ人記者が、北朝鮮第三の都市・清津出身の男女六人の半生を克明に再現する。各国メディアで絶讃された話題の書。
収容所で生まれ育った脱北青年の凄絶な半生。過酷な労働と飢え、拷問、処刑、密告が日常の「完全統制区域」―。その内情を知る、世界でただ一人の脱北者シン・ドンヒョクの証言をもとに、収容所の驚くべき実態と奇跡的な脱出、そして脱北後の苦悩を、『ワシントン・ポスト』の元支局長が迫真の筆致で描く。
Comment by Ihavenocomments 2738 ポイント
スティーヴン・ホーキングの「ホーキング、宇宙を語る」
簡単なことを難しく説明するのは誰にだって出来るけど、俺みたいなアホ相手でも量子力学が分かるように説明出来るためには真の天才じゃないと無理。
Comment by dr_doo_doo 2 ポイント
↑似たような作品でレイ・カーツワイルの「How to Create a Mind」
人間の脳がどのように思考しているかについての最近の神経学研究について分かりやすい言葉で書かれている。
読み物として面白いし、人間の生活に脳がどれ程機能しているかってことが沢山分かって驚くよ。
この宇宙はどうやって生まれ、どんな構造をもっているのか。この人類の根源的な問いに正面から挑んだのが「アインシュタインの再来」ホーキングである。難病と闘い、不自由な生活を送りながら遙かな時空へと思念をはせる、現代神話の語り部としての「車椅子の天才」。限りない宇宙の神秘と、それさえ解き明かす人間理性の営為に全世界の読者が驚嘆した本書は、今や宇宙について語る人間すべてにとって必読の一冊である。
Comment by way_fairer 2429 ポイント
デール・カーネギーの「人を動かす」
Comment by [deleted] 67 ポイント
↑それと「権力に翻弄されないための48の法則」や「孫子」
この三冊は自分自身や他人との関係をより良くするのに役立つ。
あらゆる自己啓発書の原点となったデール・カーネギー不朽の名著。
人が生きていく上で身につけるべき人間関係の原則を、
長年にわたり丹念に集めた実話と、実践で磨き上げた事例を交え説得力豊かに説き起こす。
深い人間洞察とヒューマニズムを根底に据え、
人に好かれて人の心を突き動かすための行動と自己変革を促す感動の書。本書は、パワーに翻弄されずに、抜け目なく生きていくための手引書である。古代中国、ルネッサンス期イタリア宮廷の権謀術数から、色事師の恋の駆け引き、天才詐欺師の手口まで、敗れ去った者たち、勝ち残った者たちの実際の行動と言葉が盛り込んである。法則にしたがった場合とそむいた場合の結果がどうなったかは、歴史が証明している。
Comment by [deleted] 1009 ポイント
ケビン・ミトニックの「欺術(ぎじゅつ)―史上最強のハッカーが明かす禁断の技法」
他人の大半の個人情報をいかに簡単に入手できるかってことが分かって目から鱗が落ちる。
セキュリティはどのように破られ、情報はいかにして盗まれるのか。史上最強と謳われた伝説のハッカー、ケビン・ミトニックがはじめて明かす、ソーシャルエンジニアリング(欺術)の手口。推理小説よりも面白い事例とエピソードが満載。
Comment by gogo_gallifrey 867 ポイント
エリ・ヴィーゼルの「夜」はこのスレの趣旨に合ってる?
合ってなかったとしてもこの書き込みでこの本を読んでくれる人が現われてくれればと思う。
Comment by DavidJerk 3 ポイント
↑読んだよ。今のアメリカ合衆国の一部の学校じゃこれ必読書になってたはず。
よく練られた文章で、読み終わった日は一日中鬱になってた。
15歳の少年が経験したアウシュヴィッツを静かに崇高に綴った自伝的小説。死の淵から“人間性”“信仰”“愛”とは何かを問いかける永遠の古典を改訳でおくる。
Comment by exactly_one_g 712 ポイント
ダレル・ハフの「統計でウソをつく法」
正しい情報を誤解を招くように用いることが出来ることについて書かれているものでサクッと読める。
Comment by redfaux0 1 ポイント
↑君ならネイト・シルバーの「シグナル&ノイズ 天才データアナリストの「予測学」」も気に入ると思う。(既にコメント欄に書き込まれているだろうけど・・・)
だまされないためには、だます方法を知ることだ!
かの有名な英国の政治家ディズレーリは言った――ウソには3種類ある。ウソ、みえすいたウソ、そして統計だ――と。確かに私たちが見たり聞いたり読んだりするものに統計が氾濫しているし、「平均」とか「相関関係」とか「トレンド」とか言って数字を見せられ、グラフを示されると、怪しい話も信じたくなる。しかし、統計数字やグラフは、必ずしも示されている通りのものではない。目に見える以上の意味がある場合もあるし、見かけより内容がないかもしれないのである。私たちにとって、統計が読み書きの能力と同じぐらい必要になっている現在、「統計でだまされない」ためには、まず「統計でだます方法」を本書によって知ることが必要なのである!大統領選挙での「オバマの勝利」を二度にわたり完璧に予測し、全米中を騒然とさせた天才的データサイエンティスト、ネイト・シルバーによる話題の書。金融市場、天候、政治(選挙)、プロスポーツなど、さまざまな分野における予測の重要性と精度、失敗例・成功例などに具体的に言及しながら、複雑に絡み合った情報のなかに混在するシグナル(予測の手がかり)とノイズ(雑音)の見分け方、陥りやすい落とし穴、予測の精度を高めるための手法などを平易な言葉で解説する。
Comment by TheOneBritishGuy 69 ポイント
ジョン・ロンソンの「サイコパスを探せ! 「狂気」をめぐる冒険」
情報たっぷりで面白い!
ある日、世界中の学者のもとに届けられた一冊の奇妙な本。エッシャーの細密画、切り抜かれた単語、謎のメッセージ…犯人探しに駆り出されたロンソンは、狂気が社会に与える巨大な影響を目の当たりにして―。
Comment by PantsFerret 120 ポイント
フィリップ・ジンバルドー(スタンフォード監獄実験を行った人物)が書いた「ルシファー・エフェクト ふつうの人が悪魔に変わるとき」をお勧めする
考案者が初めて明かす「スタンフォード監獄実験」の全貌と悪をめぐる心理学実験の数々、アブグレイブ刑務所虐待の真相。人間の知られざる「悪」の本性とは?戦争、テロ、虐殺、施設・家庭での虐待、いじめ、差別、企業の不正…人を悪に走らせる「元凶」を暴く衝撃の書。
Comment by Beardivism 123 ポイント
エドワード・ハーマンとノーム・チョムスキーの「マニュファクチャリング・コンセント マスメディアの政治経済学」
マスメディアはそのシステムのために、事実を伝えることができない。私たちにもたらされるニュースは、プロパガンダ・モデルの「5つのフィルター」を通過したものだけだ。「合意の捏造」の形成過程を膨大な事例を比較検討して解き明かす、現代メディア論の最高傑作。
Comment by copycat042 89 ポイント
ヘンリー・ハズリットの「世界一シンプルな経済学」
あとフレデリック・バスティアが書いたものは全部。
原題はEconomics in One Lessonで1946年初版。One Lessonとは、「経済学とは、政策の短期的影響だけでなく長期的影響を考え、また、一つの集団だけでなくすべての集団への影響を考える学問である」という原則。この原則に従って、税金、公共事業、関税、政府による価格安定策、最低賃金法などについて明快に論じていく。
フレデリック・バスティア(Frederic Bastiat, 1801年6月30日 - 1850年12月24日)は、フランスの経済学者。
1845年に『経済弁妄』(林正明訳 丸家善七 1878年)を書き上げる、その後、1849年に『理財要論』(山寺信炳訳 博文社 1880年)、1850年には『経済的調和』(土子金四郎訳 哲学書院 1888年)や『La Loi』を出版。
フレデリック・バスティア
Comment by greyexpectations 548 ポイント
ステファン・バッチェラーの「ダルマの実践 : 現代人のための目覚めと自由への指針」
この著者は無神論系仏教徒であえて仏教のスピリチュアルな側面を削り取ってその純粋な思想面に着目してる。特に悲しみとか苦しみとかの対処について。
これは旦那が突然死した直後(それで私も自殺しそうになるほど鬱になった)に渡されて読んだものなんだけど、かなり私にとって益になった。
Comment by evergreen35 3 ポイント
↑Bhante Gunaratanaの「Mindfulness in Plain English」も良い本。
どうやって瞑想するかを学びたい人にとっては。
現代人が直面している様々なディレンマに対応する真の仏教とは、答えと慰めを与えるものではなく、問いとチャレンジを促すものである。今、欧米で最も注目されている仏教の新しい流れを日本に初めて紹介。
Comment by mrbooze 275 ポイント
「ブラック・スワン: 不確実性とリスクの本質」
真面目にこれはほんとに大事な本。
大半の人はほとんど起きないことの確立やリスクを評価するのがド下手。
それが得意だと思っているような人ですらそう。
Comment by Xzorg 22 ポイント
↑ナシム・ニコラス・タレブのこの本と「まぐれ―投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか」であらゆることに対する見方が変わった。
前著『まぐれ』同様、発売直後から、人間の思考プロセスに潜む根本的な欠陥を、不確実性やリスクとの関係から明らかにして、経済・金融関係者の話題をさらった。さらに、「サブプライムローン危機」が発生すると、「誰一人予想もしなかったインパクトのある事象」が起こる原因を原理的に明らかにした書として爆発的に読まれ、全米で150万部超の大ヒットを記録している。人はどうして、投資で儲かると自分の実力だと思い込み、損をすると運が悪かったと思うのか?トレーダーとしての20年以上にわたる経験と、数学、行動経済学、脳科学、古典文学、哲学等への深い知識と鋭い洞察をもとに、金融市場や日常生活において偶然や運が果たしている隠れた役割と、人間の思考と感情との知られざる関係を鮮やかに描き出す最高の知的読み物。
Comment by Djmancewiz 251 ポイント
クリストファー・マクドゥーガルの「Born to Run 走るために生まれた: ウルトラランナーVS人類最強の“走る民族”」
Comment by Kylehansen224 48 ポイント
↑そうそう。自分がランナーじゃなくてもね。
Comment by dracarys_dude 2 ポイント
↑僕はランナーですらないけど食事や運動について良い意味で見方が変わった。
この冒険は、たったひとつの疑問からはじまった。「どうして私の足は走ると痛むのか?」その答えを探すなかでクリストファー・マクドゥーガルは世界でもっとも偉大な長距離ランナー、タラウマラ族に行きつく。その過程でわかったこと―わたしたちがランニングについて知っていることはどれもすべてまちがいだ―
Comment by MinuteInsanity 207 ポイント
自分を見失った人によって書かれた「禅とオートバイ修理技術―価値の探求」
それを二度と繰り返さないようにするための機知が随所に溢れてる。
自分が何かに関して瀬戸際にいると思っている人にはこの本は助けになると思う。
Comment by kid_boogaloo 48 ポイント
↑これは小説だから厳密にはノンフィクションではない(確か実話をフィクション化したものだったはず)だけど皆読んだ方が良いってことには同意する。
Comment by Massless 10 ポイント
↑これ本屋では「思想(Philosophy)」コーナーに置いてある所しか見たことないからノンフィクションってする方が合ってると思う。
Comment by anubus72 3 ポイント
↑小説の形式をとった「思想」だよ。
かつて大学講師であった著者は失われた記憶を求め、心を閉ざす息子とともに大陸横断の旅へと繰り出す。道中自らのために行なう思考の「講義」もまた、バイクの修理に端を発して、禅の教えからギリシャ哲学まであらゆる思想体系に挑みつつ、以前彼が探求していた“クオリティ”の核心へと近づいていく。だが辿り着いた記憶の深淵で彼を待っていたのはあまりにも残酷な真実だった…。知性の鋭さゆえに胸をえぐられる魂の物語。
Comment by Plaidpony 150 ポイント
「四つの約束」
この本を読んで自信がついたし物事を客観的に捉えられるようになった。
古代メキシコの「トルテック」の智恵にもとづいた、我々を覚醒させ、人生をすみやかに変え、真の自由と幸福をもたらすことができる力強い教え。苦しみを生む自縛的信念から逃れる方法を説く。
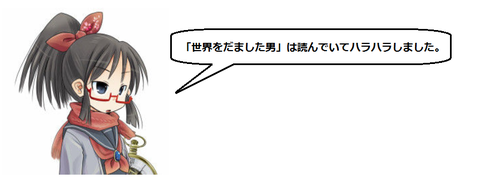
20世紀最大の詐欺師―それはわたしだ。あるときはパンナムの副操縦士。あるときは病院のレジデント。あるときは法律家。またあるときは大学講師。偽造小切手だけで、21歳までに稼いだ金額はしめて250万ドル。全米50州はおろか、26ヵ国の警察から追われたが、美食もすてきな車も魅力的な女も豪奢な住まいも思いのままだった…。稀代の犯罪者が明かす、驚くべき至芸の全貌。


























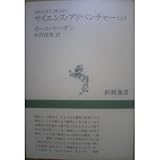






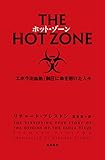







![夜 [新版]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51VMUzxra7L._SL160_.jpg)







![ブラック・スワン[上]―不確実性とリスクの本質](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41YtC8L14BL._SL160_.jpg)