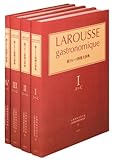海外の反応をまとめました。
外国人「大阪市とサンフランシスコの姉妹都市関係が解消、慰安婦像に抗議」
米サンフランシスコと姉妹都市を解消 慰安婦像巡り
米サンフランシスコ市が昨年11月、市民団体寄贈の旧日本軍の従軍慰安婦像を受け入れたことで、大阪市の吉村洋文市長は2日、同日付で姉妹都市関係を解消する通知文を送った。大阪市は9月末までの撤回を求めたが、返答がなかった。直接対話が実現しないまま、60年以上続いた友好関係が首長の政治的判断で消える形になった。(毎日新聞)引用:Reddit
(海外の反応)
1 万国アノニマスさん
万国アノニマスさん
戦時中に日本が利用した慰安婦を象徴する像がアメリカの都市に出来たことに抗議して
大阪市が60年に渡るサンフランシスコとの姉妹都市関係を解消した
大阪市が60年に渡るサンフランシスコとの姉妹都市関係を解消した
2 万国アノニマスさん
万国アノニマスさん
これは残念
3 万国アノニマスさん
万国アノニマスさん
戦争犯罪を思い出させるから日本が怒ってるということか
【韓国の反応】日本、「旭日旗」論議で自衛艦の韓国観艦式への派遣キャンセル
韓国人「末期ガン患者の夢を叶えた任天堂…感動秘話」
16歳の少年が13歳の彼女とキスして懲役4年6ヶ月の判決は妥当か!? 海外の反応。
日本のレッドブルファンは別次元だ(海外の反応)
アメリカ人「世界各国の残念すぎる家を貼ってみよう」
韓国人「日本メディアさん、韓国を除外したグラフを作成してしまう(笑)」
「自分の専門分野において『聖書』的地位にある本」海外のまとめ
Comment by TheRealJonat※基本的に原題のまま表記し、訳書が見つかったものは()内に邦題を入れています。
君たちの専攻、専門、興味があったり趣味である分野における「聖書」はなに?
君たちが興味ある分野で最も価値があり、必須であり、基本的な文献は?
reddit.com/r/AskReddit/comments/9b6bn1/what_is_the_bible_of_your_field_of_study/
関連記事
「外国人がお気に入りの『ディストピア小説』を紹介していくスレ」海外のまとめ
外国人「文章力のある歴史家が書いたお勧めの著作を教えてほしい」海外のまとめ
外国人「お勧めのノンフィクション書籍を紹介していく」海外のまとめ
Comment by claireauriga 3972 ポイント
「Perry's Chemical Engineer's Handbook」
大学で第一学年時に優れた成績を残したらこれを貰えるのが伝統になってる。
ページは聖書や辞書みたいにペラッペラ。
この本に記載されている化合物の温度依存の熱容量についてどうしても調べなくてはならない時が来るまでは高価なドアストップ。
Comment by IxIZ0DiAKIxI 812 ポイント
↑カナダで働いてる土木技師だけどその気持ちわかる。
鉄やコンクリート、木材のハンドブックの後にはカナダの建築基準や高速道路基準が待ち構えてる・・・
何か分析しようとしたら必要なページ数が膨大。
Comment by yagya_senixx 50 ポイント
↑まさかこのスレでその本を見るとは思わなかった!懐かしい記憶が一気に蘇った!
Comment by munching_brotatoe 8 ポイント
↑確かにその通り。その本は化学工学分野における聖書。
Comment by OntheOctave 6 ポイント
↑うちの大学は俺が入学する前にその伝統やめてしまってる。
もうこの業界に入って五年になるのに未だに一冊も持ってないわ。
3:〈話〉無用の長物、不要になった物◆ある程度重みがある電子機器、厚い本などについて「重しには使えるが本来の用途では役立たない」というほどの意味。
doorstop
Comment by courtney_coke 9 ポイント
「Ugly's Electrical References」は電気技師には最高の本!
Comment by FluffyMcSquiggles 8 ポイント
トランペット奏者には「Arban's Methods」
トランペット奏者にとってはこの本は聖書。
収録内容:
■序文
■音程とリズムの基本練習について
■スラーの練習について
■音階の練習について
■装飾音の練習について
■音の跳躍と和音の練習について
■タンギングの練習について
Comment by wushulubis 3269 ポイント
「Player's Handbook」、「Monster Manual」、それに「Dungeon Master's Guide」
Comment by stubbjmisc 70 ポイント
↑これもう三位一体だろ。
Comment by MajorStoney 9 ポイント
↑この書き込みを見るためにこのスレ開いた。
Original Dungeons & Dragonsは基本セットが箱に入って売られたボックスタイプの製品だったが、AD&Dは基本ルールブックが書籍タイプで販売された。Original Dungeons & Dragonsの数多くの追加ルールを統合した結果、基本ルールブックで扱うルールやデータの量が膨大なものとなったため、基本ルールブックは「プレイヤー用のルールブック(Player's Handbook)」「ダンジョンマスター(DM)用のルールブック」「モンスターのデータ集」の三種類に分けられた。基本ルールブックを三分冊する形式は後にアドバンストとクラシックが統合されたD&D3版以降にも受け継がれた。
アドバンスト・ダンジョンズ&ドラゴンズ
Comment by Malleon 7 ポイント
分子生物学、細胞生物学の分野ではアルバート等による「Molecular Biology of the Cell(細胞の分子生物学)」
内容の濃い1400ページの本だけど丁寧に書かれてる。
これを全体的に学んだ後では論文を読む時間がかなり短くなったことに気付いた。
世界10か国語以上に翻訳され,世界中で読まれている第一級のテキスト『細胞の分子生物学』の最新版がついに登場! 『第6版』は,最新情報を網羅した大幅改訂版です。
細胞生物学,分子生物学のホットな話題が満載!
ES細胞やiPS細胞/がんの最新治療法/細胞の可視化の新手法……といった最新の研究成果を網羅的に収録。
各分野のホットな話題が満載で,さらに充実した内容となりました。
Comment by SpookyPapa 6 ポイント
文筆分野でお気に入りなのは「The Anatomy of Story: 22 Steps to Becoming a Master Storyteller」
Comment by FamilyMan709 1976 ポイント
「The silver spoon(シルバースプーン)」
イタリア料理の基本書の一冊で基本的なトマトスープからパスタや梨まであらゆる調理をカバーしてる。
2000以上のレシピがシンプルな形式で記載されていて、これを読めば参考になるしページをめくるごとにワクワクするよ。
Comment by ColdNotion 201 ポイント
↑これには同意!
ネットで簡単にレシピを調べられるようになった今でもイタリア料理を作るときにはこの本にかなり頼ってる。
かなり広い範囲をカバーしてるし個人的経験から言えば記述にはかなりの信頼性がある。
唯一不満があるとすればうちのアパートにあるいくつかの家具よりも重いってこと。
Comment by ScarfaceClaw 6 ポイント
↑その本については色々と聞いたことがある。
イタリアじゃ信じられないくらい人気がある本だけど、私が聞く限りでは「Marcella Hazan's Essentials of Classic Italian Cooking」の方がより万人向けって感じ。
私が持ってるのはこっちの方だけど一番よく利用した料理本。
Comment by sayiansaga 3 ポイント
↑てっきりマンガの事を言ってるのかと。
Comment by FamilyMan709 3 ポイント
↑俺はセル編が好きだった。
イタリアの家庭で60年間愛され続けてきたイタリア料理のバイブル「シルバースプーン」の改訂版。
新しい「シルバースプーン」は、進化する現代の料理への要望に応え、かつ料理初心者にも親しみやすい内容へ改訂。
本改訂版は、初心者から熟練者まで、どのような人でも完璧なイタリア料理が作れるように、内容を見直した本場の信頼できるレシピ集です。
大切な方への贈り物としてもお奨めします。
Comment by crusader86 670 ポイント
「Wheelock's Latin」と「アエネーイス」は現代でラテン語を学ぼうとする人間には必須の本。
Comment by CN_W 170 ポイント
↑「アエネーイス」?じゃあもう「Gallia est omnis divisa in partes tres」はないの?
Comment by arrogantsword 78 ポイント
↑数年前だけどうちの大学の講義じゃ未だに「Wheelock's Latin」→カエサルって流れだった。
Comment by CercaTrova6 25 ポイント
↑あと「Lingua Latina Per Se Illustrata」も。
Comment by VerySecretCactus 8 ポイント
↑「Lingva Latina」の方が優れた教科書だと正直思う。
Comment by The_Elder_Potato 2 ポイント
↑昨日ラテン語の授業のためにその本買ったばかり!
大学時代にラテン語の授業で使っていた教科書は、"Wheelock's Latin"という本である。 英語で書かれているが、ラテン語の学習用としては、もっとも多く使われている。
Wheelock's Latin (6th edition) 練習問題解答
『アエネーイス』(古典ラテン語: Aeneis)は、古代ローマの詩人ウェルギリウス(前70年–前19年)の叙事詩。全12巻。イーリオス(トロイア)滅亡後の英雄アエネーアース(Aenēās、ギリシア語ではアイネイアース Αἰνείας)の遍歴を描く。アエネーイスは「アエネーアースの物語」の意。
ウェルギリウスの最後にして最大の作品であり、ラテン文学の最高傑作とされる。この作品の執筆にウェルギリウスは11年(前29年–前19年)を費やした。最終場面を書き上げる前に没したため未完である。彼は死の前にこの草稿の焼却を望んだが、アウグストゥスが刊行を命じたため世に出ることになった。『アエネーイス』以後に書かれたラテン文学で、この作品を意識していないものはない。
アエネーイス
「ガッリアは全体として三つの部分に分かれている」と訳せます。
カエサルの『ガリア戦記』冒頭の言葉です。
Gallia est omnis divisa in partis tres
Comment by _Cah1r_ 31 ポイント
手品師だと「Expert at the Card Table」
Comment by majik89d 7 ポイント
↑カードマジシャンにとっては、だろ。
コインマジシャンならJ.B. Boboの「Modern Coin Magic」
Comment by DetromJoe 5 ポイント
↑文字通りの意味で聖書。
名著である以前に、とんでもない奇書です。著者の S.W.Erdnase はプロのイカサマ師です。そんな著者がカードを使ったイカサマの技法を惜しげもなく晒してしまいます。1902年にこの本が出版された時、マジック界には計り知れない衝撃が走ったそうですが、イカサマで生計を立てていた人達の衝撃に比べれば、大した事はないのかもしれません。この本は、相手を騙す為のアドバイスが所々に差し込まれていると同時に、相手を楽しませるマジックも紹介しているという奇妙な構成です。
THE EXPERT AT THE CARD TABLE
Comment by cygnus1953 22 ポイント
航空業界だと「FAR/AIM (Federal Aviation Regulations and Aeronautical Information Manual)」
Comment by gunterpt8t0 3 ポイント
↑それと航空交通管制分野だと「FAA JO 7110.65」
これがアメリカの航空法に関して掲載されている本になります。Student Pilot必携の書です。
Federal Aviation Regulations and Aeronautical Information Manual 2017 (Far/Aim)
FAR AIMとありますが、後半のAIMは航空関係のマニュアル情報をまとめたものです。
チェックライド前準備① FAR/AIMとAVIATION ACRONYMS
Comment by DisorientingPan 431 ポイント
Henry Carrollの「Read This If You Want to Take Great Photographs(偉大な風景カメラマンが教える写真の撮り方)」
入門書としては素晴らしいし、何か撮影したいと思ったようなときのリファレンスブックとしても素晴らしい。
Comment by Namnodorel 6 ポイント
↑なんかアクセス稼ぎみたいなタイトルだな。
※原題を直訳すると「素晴らしい写真を撮影したいならこれを読め!」になります。
関連記事
外国人「歴史上の出来事の概要をアクセス稼ぎタイトル風に要約していく」海外の反応
外国人「アニメの概要をアクセス稼ぎタイトル風に要約していく」海外の反応
「著名な本のタイトルを『アクセス稼ぎ』風にするスレ」海外の反応
何を、いつ、どのように──
ビックリするような素敵な風景写真を撮るにはこの3つが決め手です。
「何を」は撮る人が何に刺激を受けるかをしっかり掴まえることです。
手つかずの自然、意外性を見せる工業地帯、歴史的に価値ある場所など、
撮りたいものを見付けること。
「いつ」は取る対象に適した時間をしっかり把握すること。
早朝なのか、日中なのか、夕暮れなのか、それとも真夜中なのか。
「どのように」は撮るテクニックのこと。
写真をシャープに見せるのか、ボケを効かせるのか、構図はどうするか、などなど。
この3つの決め手を実際の作品を解説しながら、詳しく解説しています。
自分をイメージする風景写真を撮るためのヒントが満載です。
Comment by RiseAnShineMrFreeman 30 ポイント
製造技師だけど、製造工場では大野耐一の「トヨタ生産方式――脱規模の経営をめざして」はまさに「聖書」と呼ばれてる。
◆40年にわたって読み継がれる古典的名著! ◆
いまや誰もが知るほど有名になった「トヨタ生産方式」。本書はその基本思想を構想し、構築し、実践した大野耐一(元トヨタ自工副社長)が著した生産管理および経営理念の世界的バイブルである。
トヨタ生産方式の真髄は「徹底したムダの排除」にある。それを実現するための柱が「ジャスト・イン・タイム」と「自働化」であり、この2つをスムーズに有機的に活かす手段が「かんばん方式」である。
欧米における自動車工業の大量生産に対抗し勝ち残るため、トヨタは試行錯誤を繰り返し、純粋に日本オリジナルの生産システムを追究するなかで、これらの思想や方式を生み出した。
年間生産台数が1000万台を超え、世界トップを争うトヨタの「ものづくりの原点」が本書にはすべて詰め込まれている。
Comment by Theostry 19 ポイント
他言語話者に英語を教える人にとっては教育学だとJim Scrivenerの「Learning Teaching」で、文法だとMichael Swanの「Practical English Usage(オックスフォード実例現代英語用法辞典)」
後者は英語を使って仕事している人やそのスキルを磨きたい人ならレファレンスツールとして持っておくことをお勧めする。
実用的語法辞典のスタンダードとして定評ある第3版を、従来のABC順から、文法篇28節(320項目)と語彙篇3節(315項目)に分けて再構成、より使いやすくなった新改訂版。「文法篇」では品詞、時制、動詞構文、情報構造などの主題別に単語から複雑な文の組み立てに至る筋道をつかめるように配慮。「語彙篇」では特に誤りやすい語句をまとめ、現代英語の変化を見据えて解説をアップデート。メール・電話・新聞の見出し・発音・正書法・挨拶など日常生活の様々な場面で出会う英語の情報も充実。
Comment by drew_writes 418 ポイント
聖書。
あと聖書の注釈書。これは聖書を理解するのに重要。
神学の学生です・・・
Comment by circuspunk- 24 ポイント
僕の専門分野は鉱物学、岩石学(地質学)だけど聖書はDeer、HowieそれにZussmanによる「An Introduction to the Rock Forming Minerals」
全ての岩石地質学者はこの本を所有しているべき。
Comment by skaska23 24 ポイント
サトシ・ナカモトの「ホワイトペーパー」
Comment by MidnightDemon 3 ポイント
↑何の分野?
Comment by rk-imn 6 ポイント
↑これはビットコインを生み出した人が書いたビットコインについての論文だったはず。
サトシ・ナカモト(ラテン文字表記: Satoshi Nakamoto)は、ビットコインプロトコルと、そのリファレンス実装であるビットコインコア (Bitcoin Core/Bitcoin-Qt) を作ったことで知られる人物の称する氏名。本名であるか、そもそも個人であるかどうかを含め、正体は不明。
サトシ・ナカモト
ビットコインホワイトペーパーとは、2008 年 10 月 31 日に Satoshi Nakamoto と名乗る人物により公開されたビットコインのおおまかな仕組みが書かれた論文です。原文は英語で、タイトルは「Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System」です。多くの方が長大な論文を想像するかもしれませんが、注釈を含めてもたった 9 ページの短い論文です。
金融機関などの第三者を通さず低コストで取引できる電子マネーのアイデア。中央にサーバーを置かず、ネットワークで接続された端末同士でデータをやり取りするピア・ツー・ピア(P2P)という仕組みを使い、プルーフ・オブ・ワークにより取引情報の改ざんを実質的に不可能にする仕組みについて説明されています。
ビットコインホワイトペーパー
Comment by Ineedanotherface 630 ポイント
アニメーターやアニメーションに情熱を持ってる人だとRichard Williamsの「The Animator's Survival Kit(アニメーターズ・サバイバルキット)」
Comment by DeltaCore12 152 ポイント
↑「The Illusion of Life(ディズニーアニメーション 生命を吹き込む魔法)」もね。
アカデミー賞をトリプル受賞した映画「ロジャー・ラビット」のアニメーション監督が自ら解説する、実用的なアニメーション制作マニュアル。初心者からエキスパートまで、全てのアニメーターが必要とする基本原則を提供する。
本書は、ディズニーのキャラクター・アニメーション技術を進歩させる上での試行錯誤の苦労について語るとともに、歴史に残る原画を数多く披露。それらの原画は、ミッキーマウスやドナルドダック、白雪姫やバンビなど、アメリカ文化の中でもっとも愛されているキャラクターを生み出すのに使われたもので、『ファンタジア』『ピノキオ』といった傑作の名場面を発展させるときに初期の段階で描かれたスケッチも掲載されている。
Comment by yanhamu 6 ポイント
金融分野ではJohn Hullによる「Options, Futures and Other Derivatives(フィナンシャルエンジニアリング)」
これのニックネームは「the hull」
歴史的名著(“Options, Futures, and Other Derivatives")の日本版として6年ぶりとなる本書では、CVA・DVAを扱う章を新たに設けたほか、OTCデリバティブにおける清算、信用危機対応etc
デリバティブ業務・市場を取り巻く顧客とマーケットの変化、国際的金融規制、リスク管理に関する時代の要請を受けた金融工学の変化をあますことなくカバー。
すべての“デリバティブ関係者"の理論・技術の習得、実務への応用に必備の一冊
Comment by Noxocopter 5 ポイント
これはあくまで一つの意見でしかないけど、ジョン・ロールズの「正義論」
『正義論』(せいぎろん、A Theory of Justice)は、1971年にジョン・ロールズにより著された政治哲学の著作。1921年に生まれ、ハーバード大学で教鞭をとっていたロールズは本書で正義理論を展開することで、それまで停滞していた戦後の政治哲学の議論に貢献した。公民権運動やベトナム戦争、学生運動に特徴付けられるような社会正義に対する関心の高まりを背景とし、その後の社会についての構想や実践についての考察でしばしば参照されている。
正義論 (ロールズ)
Comment by BriefcaseWanker88 2258 ポイント
セキュリティーガード。
George Thompson著の「Verbal Judo: The Gentle Art of Persuasion」
これを読むと効果的なコミュニケーションについての考え方が変わるし、プロになるべく努力しようって気になる。
Comment by Belgand 424 ポイント
↑ニコラス・ケイジが自分の家に押し入った男を「verbal judo」でやりこめたって言ってた時は何言ってんだって感じだったけど、彼は文字通りの意味でこの本の事を言ってたんだな。
Comment by CuttyAllgood 1 ポイント
↑彼女との口論のためにこの本が俺には必要。
Comment by Babyy_blue 1228 ポイント
「The Backstage Handbook: An illustrated almanac of technical information」
これは劇場技術者のための本。特に劇場大工や劇場電気技師のための。
出版されてから30年経つけど未だにみんなが持っている本。
Comment by Masterofice7 170 ポイント
↑うちの劇場には昔この本のための小さな聖堂があった。
Comment by IndianaDodge 8 ポイント
↑確かに。
うちの大学の劇場の大工として働いてたことがあるけど、うちの監督が全員入手するように強く進めていたのがこの本だった。
だから僕はこの本を一冊持ってる。この本に書かれてるくだらないジョーク大好き。
Comment by Buildinblox 6 ポイント
↑うちの大学ではこの本を「青い聖書」って呼んでた。
Comment by mrpokealot 80 ポイント
不動産業で働いてるから聖書に相当するのは「National Land Code(国土法)」
誰も読んでないし、頭の良い人の多くはこれについて語ってるけど本当にこれを気にかけてるのは面白いヘッドギアを持ってる人だけ。
つまりは聖書みたいなもの。
Comment by VoidWalker4Lyfe 9 ポイント
↑君の分野の面白いヘッドギアがどういうことか説明してくれない?
Comment by mrpokealot 20 ポイント
↑裁判官は面白いカツラ被ってるでしょ。
Comment by VoidWalker4Lyfe 4 ポイント
↑あーそういうことかw ありがとう。
Comment by Lazarus5687 56 ポイント
「シルマリルの物語」と「トールキンの書簡集」
Comment by lukethx 4 ポイント
↑その本をどの分野で使うの?ファンタジーフィクション作家とか?
Comment by Lazarus5687 20 ポイント
↑いやいや違うよ!スレタイには自分の仕事や興味のある分野や趣味における「聖書」って書かれてたから。
僕はトールキンの大ファンだから興味があるし趣味ってこと。
つまらない回答で申し訳ない・・・
Comment by lukethx 7 ポイント
↑僕もハイファンタジーの大ファンだけど、こういうレスがこのスレッドには必要だと思ってた!
書き込みしてくれてありがとうね!
『シルマリルの物語』(シルマリルのものがたり、原題:The Silmarillion、シルマリルリオン)は、J・R・R・トールキンの神話物語集。トールキンの死後、息子クリストファー・トールキンによって彼の遺稿がまとめられ、編集を加えられた上で1977年に出版された。
創世から『ホビットの冒険』、『指輪物語』の時代(太陽の時代の第三紀)にいたるまでの中つ国の歴史を扱う。これら2作で断片的に現れる英雄や神々の物語が詳細に記述されており、トールキンの創り出した世界をより深く知ることができる内容となっている。
シルマリルの物語
Comment by TitsvonRackula 855 ポイント
ジャーナリスト/編集だけど「聖書」は間違いなく「AP Stylebook(APスタイルブック)」
現物を持っているか、オンライン上で見られるようにするかのどっちか。
この分野に興味がある人全員にお勧めしている基本書の一冊はWilliam Strunk Jr.の「The Elements of Style(英語文章ルールブック)」
Comment by the_unfinished_I 275 ポイント
↑>>「不必要な言葉を省略」
この本には他にも色々参考になる事載ってるけど、この文章が他の何よりも頭に残ってる。
Comment by derleth 1 ポイント
↑俺だったら「省略」とだけ言うね。
Comment by not-nick-offerman 6 ポイント
↑「AP Stylebook」で好きなのは効率的なところ。MLAとかクソだわ。
『APスタイルブック』(英: The Associated Press Stylebook and Briefing on Media Law, AP Stylebook)は、米国のAP通信が編纂・発行するスタイルガイド。文法、句読法、表記法(大文字・略語・スペリング・数詞の使い方、スタイルの定義とルールなど)が記されたもので、もとはAP通信に勤務・提携した米国人ジャーナリストたちが文体を標準化するため作成したものである。1953年に一般向けに書籍化され、英語圏では放送・雑誌などの報道関係者のみならず、教育機関や一般企業の広報宣伝部門でも広く使われるようになった[1]。
APスタイルブック
MLA Handbook: Eighth Edition. は米国現代語学文学協会(Modern Language Association of America [MLA])が手がけたもので、合衆国および外国の大学で何世代にも渡って広く用いられてきた。
MLA論文の書き方
Comment by OddUsual 74 ポイント
「Larousse Gastronomique(ラルース料理大事典)」
最も専門的な調理に関する本で独自のレシピのコレクションも載っていて「聖書」と呼ばれている。
新ラルース料理大事典(LAROUSSE gastronomique)は、60年間に3度の大改定を加えられ、世界から高い評価を得ている料理総合大事典です。 最新日本語版の本書は、現代フランスの名シェフ、評論家、ジャーナリスト、作家からなる「編集委員会」が全面参加。 基調な最新料理情報が盛り込まれています。
Comment by PennName27 55 ポイント
Strunk & Whiteによる「The Elements of Style(英語文章ルールブック)」
文法家なら全員がこの本のことを知ってる。
ただこれは完全に総合的な文法書というわけではないから聖書ではないかも。
どっちかというとモーセの十戒かな。聖書の一部分だけど有名な箇所って意味で。
Comment by LuxTx10 11 ポイント
↑その本のことは自分の文体を改善しようとするフィクション作家の方がよく知ってる。
Comment by idotaxreturns 807 ポイント *
公認会計士だけどそれは「Internal Revnue Code(内国歳入法)」
トランプの税制改革によって新約聖書が作られているところだからこれは旧約聖書で、誰も気にしないモーセの十戒のようになってる。
みんなこれを読むべきと言ってるけど、これは73000ページもあるから3ページも読むと眠ってしまうというのは全員が知っていること。
Comment by VTArmsDealer 2 ポイント
↑婚約者が公認会計士の勉強してるけど新しい税制度がどうなるか分からなくて戦々恐々としてる。
Comment by caohbf 71 ポイント
「Harrison's Principles of Internal Medicine(ハリソン内科学)」
切ったりすることでは解決できないほとんどのことについて載ってある。
Comment by exikon 5 ポイント
↑そうそう。ドイツに留学していた時ですら我等が「聖書」はどの医者のオフィスにも置いてあった。
Comment by CommieGhost 5 ポイント
↑これはガチ。「ハリソン内科学」はPortoの「記号学」と共にあらゆるところに存在する。ここはブラジルね。
ハリソン内科学 (Harrison's Principles of Internal Medicine) はアメリカで発行されている内科学の教科書である[1]。1950年に最初の版が出版され、2018年1月現在第19版が最新版である。医療従事者に使用されている内科学の教科書として最も評価されている本である[2]。
ハリソン内科学
Comment by defiantlynotathrowaw 37 ポイント
これはかなり限定的な分野だけどロゼッタ・ストーンは歴史家にとっては極めて重要。
これがなかったらエジプトの歴史についての知識はかなり浅いものになっていたはず。
Comment by 1forthethumb 3 ポイント
↑俺は「The History of the Peloponnesian War(戦史)」の方を考えてた。
ロゼッタ・ストーン(ロゼッタ石、仏: Pierre de Rosette, 英: Rosetta Stone)は、エジプトのロゼッタで1799年に発見された石版。
紀元前196年にプトレマイオス5世によってメンフィスで出された勅令が刻まれた石碑の一部である。
碑文は古代エジプト語の神聖文字(ヒエログリフ)と民衆文字(デモティック)、ギリシア文字の三種類の文字で記述されている。細かい違いはあるが、本質的には同一の文章が全部で三つの書記法で著されていると早くに推測され、1822年、ジャン=フランソワ・シャンポリオンもしくは物理学者のトマス・ヤングによって解読された。これによってロゼッタ・ストーンはエジプトのヒエログリフを理解する鍵となり、他のエジプト語の文書も続々と翻訳が可能になった。
ロゼッタ・ストーン
『戦史』(せんし、希: Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου、英: History of the Peloponnesian War、日: ペロポネソス戦争史)は、古代ギリシアのアテナイ出身の歴史家トゥキディデスが著した歴史書である。
アテナイの興隆と衰退、ペロポネソス戦争(紀元前431年–紀元前404年)の経過を記録した本書は全8巻からなる(マルケリノスの「トゥキディデス伝」によれば13巻に分けた者もいるが、多くは8巻としているようである)。なおこの題名は、後世に付けられたものであり、『歴史』、『ペロポネソス戦争史』とも呼ばれる。本書は客観的かつ実証的な叙述で知られ、物語的叙述であるヘロドトスの『歴史』(ヒストリア)と対比されることが多い。
戦史 (トゥキディデス)
Comment by Cows_Killed_My_Mom 991 ポイント
心理学は「DSM(精神障害の診断と統計マニュアル)」
Comment by SofSofTheKittyCat 122 ポイント
↑臨床心理学じゃん・・・
Comment by Cows_Killed_My_Mom 6 ポイント
↑どの心理学の分野でも聖書として考えられてるよ。
その多くが臨床に焦点を当てられているからと言ってそれが他の点では重要ではないってことにはならないし。
Comment by Greyblades 23 ポイント
↑神経認知の領域を研究している場合はそこまでじゃない。
Comment by havebeenfloated 48 ポイント
↑それ欠陥があるよ。聖書と同じように。
Comment by KingGorilla 1 ポイント
↑聖書が未完成という可能性もある。
精神障害の診断と統計マニュアル(せいしんしょうがいのしんだんととうけいマニュアル、英語: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM)は、精神障害の分類(英語版)のための共通言語と標準的な基準を提示するものであり、アメリカ精神医学会によって出版された書籍である。
明示的な診断基準がないため、以前の診断基準では、アメリカと欧州、また日本での東西によって診断の不一致が見られた。このような診断の信頼性の問題により、明示的な診断基準を含む操作的診断基準が1980年のDSM-IIIから採用され、操作主義の精神医学への導入であり画期的ではあった。一方で、恣意的に適用されてはならないといった弱点はいまだ存在する。依然として、どの基準が最も妥当性があるかという問題の解決法を持たず、他の診断基準体系との間で診断の不一致が存在するため、原理的に信頼性の問題から逃れられないという指摘が存在する。
精神障害の診断と統計マニュアル
Comment by severalsmallweasles 408 ポイント
「Don't Shoot The Dog(うまくやるための強化の原理 -飼いネコから配偶者まで- )」と「The Culture Clash」
現代科学に基づく犬の訓練方法。
Comment by SnarfraTheEverliving 3 ポイント
↑それと「Train the Dog in Front of You」が好き。けど「聖書」というレベルまではないな。
Comment by apocalypsebuddy 3 ポイント
↑それ犬だけじゃなくて、虎の訓練にも使える。その理論はどの動物にも当てはまる。
イルカをジャンプさせたり、イジワルな同僚を好人物にしたいとき、「強化の原理」は天からの贈り物になる。日常のあらゆる場面に応用がきく原理を紹介する。
Comment by spinozasrobot 346 ポイント
Ritchie & Kernighanの「The C Programming Language(プログラミング言語C)」
Comment by pancakeQueue 26 ポイント
↑知ってるだろうけどニックネームの付いたプログラミングの本は良書。
これと「Gang of Four book(オブジェクト指向における再利用のためのデザインパターン)」はどちらも素晴らしい。
Comment by BCMM 5 ポイント
↑これ「白の聖書」として知られてるよ。
『プログラミング言語C』(原題:The C Programming Language)は、ブライアン・カーニハン (Brian W. Kernighan) とデニス・リッチー (Dennis M. Ritchie) によって書かれたC言語についての書籍である。著者名の頭文字からしばしばK&Rと略される。
初版[1]は1978年に出版され、C言語が標準化されるまでの間リファレンス的な扱いを受けていた。1988年の第2版[2]ではANSIでの標準化 (C89) を反映して大幅に変更されている。
プログラミング言語C
ソフトウェア開発のバイブル群! 弊社がこれまでに刊行した翻訳技術書の中から、長年読者から支持され続けている名著を厳選したのが、本シリーズです。移り変わりの激しいコンピュータ業界で、普遍性を保ち続ける定番をお届けします。ソフトウェア開発の上流から下流まで、入門書からエキスパート向けまで、技術者に求められる選りすぐりの情報がここにあります。
Comment by FascistDick 292 ポイント
「The Feynman Lectures on Physics(ファインマン物理学)」
色んな物理学者のオフィスに行ったことがあるけどほとんどの棚にこの本があった。
Comment by MrBlueCharon 82 ポイント
↑その本は物理学者としてどうやって考えるかを掴むには良書だけど毎日使用する本としては他に基本書がある。
僕はこれを専門にしてるんだけど、実験物理学ならDemtröderは欠かせない。古典だとFließbachやLipschitz・・・
自分の専門によって色んな聖書がある。
Comment by striatedgiraffe 12 ポイント
↑リアルな聖書で言うのならこれだな。みんな棚に置いてあるけど触れもしない。
『ファインマン物理学』(ふぁいんまんぶつりがく、英: The Feynman Lectures on Physics)は1963年、1964年、1965年に出版されたリチャード・P・ファインマンとロバート・B・レイトン、マシュー・サンズ(en)による3巻構成の物理学の教科書である。ファインマンが1961年から1963年にかけてカリフォルニア工科大学(California Institute of Technology, 略称: Caltech, カルテック)で学部1、2年生を対象に行った講義が基になっている。
ファインマン物理学
実験物理学(じっけんぶつりがく、英語: experimental physics)は、実験や観測を通して自然現象・物理現象を理解しようとする物理学の研究方法のひとつ。理論物理学と対比される。特定の物理現象に関して物質の振る舞いを実際に観測、測定しその現象に特有な物理量ないしは物理量の変化を抽出して物質が従う法則を発見しようとするなどの研究がこれに当たる。
実験物理学
Comment by kazosk 278 ポイント
ゲームをするのが好きな僕は「孫子の兵法」
Comment by ColonelYuri 149 ポイント
↑「君主論」をマニュアルとして使用できるくらい深いゲームがあればいいのに。
Comment by 987654321- 114 ポイント
↑「EVE ONLINE」とか?
Comment by Bad_Idea_Hat 46 ポイント
↑「EVE ONLINE」のせいで「君主論」が時代遅れになった感がある。
Comment by cobrophy 10 ポイント
↑競合ゲームなら「Playing to Win(P&G式 「勝つために戦う」戦略)」が素晴らしい。
EVE ONLINE(イブ オンライン)は、アイスランドのCCP Gamesが発売している、宇宙を舞台としたMMORPG。
プレイヤーは、5,000以上の星系からなる宇宙で生活する一市民となり、各種の宇宙船を乗り回して“生活”をする。
プレイスタイルの自由度が非常に高く、戦闘、生産、採掘、商売、領有権争いなど多様なプレイスタイルがきちんと成立しつつ、プレイヤー同士が取引やプレイヤーコープを通して関係しながら生活している。
EVE ONLINE
危機に陥ったP&Gが変革を断行し、世界最強の消費財メーカーへと躍進できたのはなぜか。売り上げ2倍、利益4倍、市場価値1000億ドルに成長させた名経営者と、Thinkers50(経営思想家トップ50)の経営学者が明らかにする!
戦略を欠く企業はいずれ死ぬ。偉大な発明や製品のアイデアは、企業を誕生させ、しばらく価値を生み、市場で勝たせてくれる。しかし、どんな業界や事業にも、永続的な競争優位性を保証してくれるアルゴリズムなど存在しない。
本当に重要なのは、「勝つために戦う」戦略である。偉大な組織――企業であれ、非営利団体であれ、政治団体であれ、官公庁であれ――は、「戦うために戦う」戦略をとってはならない。勝つために戦おう。
Comment by Chromattix 303 ポイント
今日、もう15年くらい世話をしてる盆栽を剪定したんだけど、未だにこの趣味に初めて入った時に購入したColin Lewisの「The Bonsai Handbook」で学んだ知識を思い出しながらやってた。
初めてやった時は数鉢しかなかったけど今では15鉢くらいある。
それなりのレベルで剪定や整枝、植え替えのことを学べたからインターネットで調べないといけないようなことはほとんどなかった(プロレベルではないかもしれないけど僕は他にもやることがあるし)
人生の半分くらいをこの趣味と共に過ごしてるし結構上手く育てることも出来てる。
それが出来たのはこの表紙に日本のカエデが載った小さな黄色い本のおかげ。
Comment by boobfar 218 ポイント
コンピューター科学分野なら「SICP(計算機プログラムの構造と解釈)」
Comment by myw01 93 ポイント
↑それと「CLRS(アルゴリズムイントロダクション)」
Comment by Professor_Hoover 70 ポイント
↑そこはKnuthの「The Art of Computer Programming」じゃない?
数千ページもあって40年経つのに未だに改訂版の作業をし続けているという。
Comment by ithika 10 ポイント
↑どっちも良い回答。「SICP」は教育的な価値があるし「TAoCP」はレファレンスとしての価値がある。
『計算機プログラムの構造と解釈』(Structure and Interpretation of Computer Programs。原題の略称SICPがよく使われる)は、1985年にMIT出版から刊行された、計算機科学分野の古典的な教科書。
計算機科学の古典として広く認められている。
計算機プログラムの構造と解釈
世界標準 MIT 教科書!! 大変好評を博しているMITでの計算機アルゴリズムの教育用に著わしたテキストの原書3版である。前版までで既にアルゴリズムとデータ構造に関する世界標準教科書としての地位を確立しているが、より良い教科書を目指して今回、章立てを含め再び全面的な改訂を行った。 各節末には多様なレベルの問題が配置され、学部や大学院の講義用教科書として、また技術系専門家の手引書、あるいは事典しても活用できる。
『The Art of Computer Programming』は、コンピュータプログラミングに関する書籍である。様々なアルゴリズムについて、その背景や歴史まで踏み込んだ徹底的な解説を行っている。著者のドナルド・クヌース (Donald.E. Knuth) は、自身のライフワークと位置づけている。
The Art of Computer Programming
Comment by SlinderMin 90 ポイント
Steve Krugの「Don’t Make Me Think(超明快 Webユーザビリティ ―ユーザーに「考えさせない」デザインの法則)」
ユーザーエクスペリエンス分野に気軽に入門できる本
Apple、Bloomberg、Lexus などを顧客としてきた、ユーザビリティコンサルタントの第一人者にして激安ユーザーテストの伝道師 スティーブ・クルーグが説く、
ユーザーに「考えさせない」サイトの作り方。
20か国で翻訳、累計45万部超の世界的ベストセラー、ウェブ&モバイルユーザビリティの定番書『Don't Make Me Think』の日本語版です。
ちゃんと使ってもらえるサイトにしたいWeb担当者、コンバージョン率を上げたいEC担当者におすすめの一冊。超明快 Webユーザビリティ ―ユーザーに「考えさせない」デザインの法則
ユーザーエクスペリエンス(英: user experience)とは、人工物(製品、システム、サービスなど)の利用を通じてユーザーが得る経験である。しばしば「UX」と略される[1]。「ユーザー経験」「ユーザー体験」などと訳される。
よいユーザーエクスペリエンスを達成するために、ユーザビリティ工学、インタラクションデザイン、ユーザー中心設計 (UCD) あるいは人間中心設計 (HCD) などが実践される。
ユーザーエクスペリエンス
Comment by Rennick-senpai 15 ポイント
ポケモンプレイヤーの聖書は「Serebii.net」だろ。
※ポケモンデータベースサイトです。
https://www.serebii.net/index2.shtml
Comment by Tapko13 16 ポイント
コックの自分からすればEscoffierの「Guide Culinairr(エスコフィエフランス料理 LE GUIDE CULINAIRE)」
いくら讃辞を書き連ねてもなお足りない名著。そんな料理書が存在するでしょうか?
しかし、この一冊だけは、そのように形容することが許されると思います。
貴方が西洋料理、とくにフランス料理に関わるか、その道を志すのであれば、
本書を無視して通過することは不可能です。
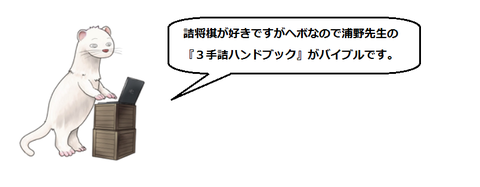
ルールを覚えたらこの一冊。基本手筋満載の3手詰200題を掲載。