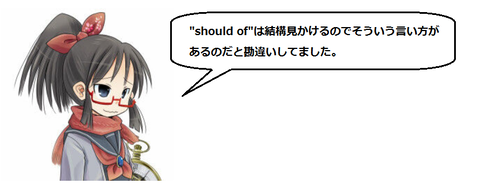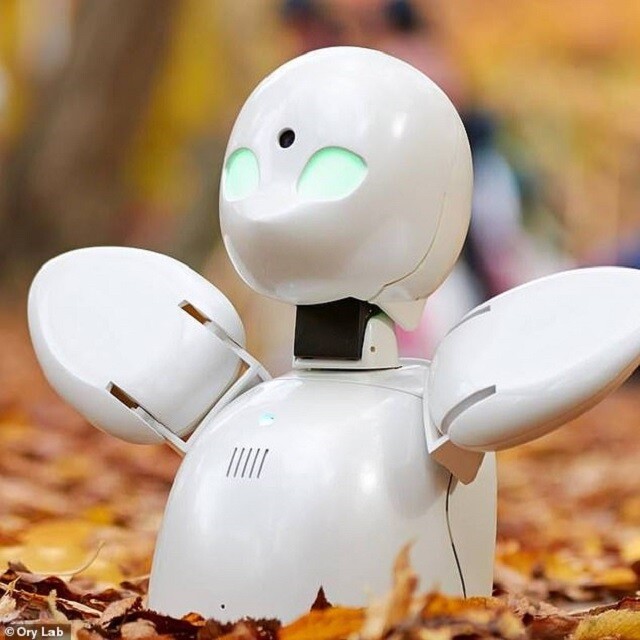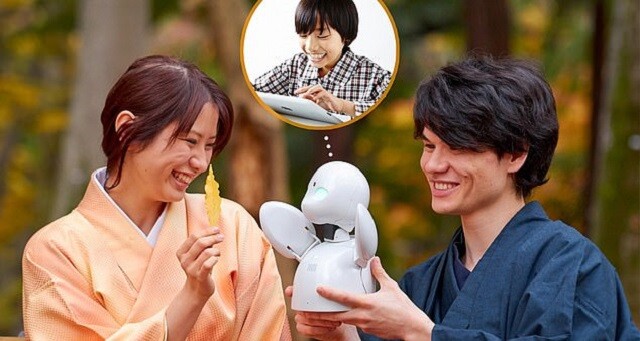Comment by Duchowicz関連記事
(ポーランド)
英語が母国語の人に聞きたいんだけど、非ネイティブが使っている英語で正しいけど変な感じがしたり古風な感じがするからネイティブは使わないみたいなのってある?
reddit.com/r/AskEurope/comments/drys2f/english_native_speakers_what_is_something_you/
「英語の否定疑問文を否定しても肯定にならないのはなんで?」海外の反応
Comment by CocoRuza1 499 ポイント
(ウクライナ)
英語が母国語ではないけどうちらは「it's normal(それは普通だ)」って言う時「it's okay」って意味で使ってる。
アメリカ合衆国で僕の靴にコーヒーをこぼした人がいたんだけど、その人が謝ってきたから僕は「大丈夫ですよ、それは普通です」って言ったら目を見開いてこっちを見てきた。
この時に自分の靴にコーヒーをこぼされるのは「it's not normal」ってことを理解したわ。
Comment by d3dev 34 ポイント
(ウクライナ)
↑彼はウクライナではそれは「it's normal」だって思ったろうなw
Comment by BenedickCabbagepatch 23 ポイント
(ロシア在住のイギリス人)
↑自分は生徒にいつも、自分がどんな感じか聞かれた時に「I'm normal」なんて言わないようにって言ってる。
生徒はそれが「нормально」って意味だと思ってるんだけど、これは典型的な「空似言葉」の例。
生徒には自分の調子を聞かれて「normal」なんて答えるのは頭のおかしい人だけだって言ってる。
Comment by Jekawi 2 ポイント
(ドイツ)
別に変でも時代遅れな言い方でもないんだけど、うちらは英語だと現在進行形を使いたがる。
例えば「I walk to school now」は文法的に正しいけどうちらはそうは言わない。
うちらはいつも「I'm walking to school」って言ってる。
Comment by kobakoba 6 ポイント
↑ドイツの学校ではうちらはそういう場面で現在形を使うのは間違いだって習ってる。
Comment by d3dev 2 ポイント
(ウクライナ)
↑いや、文法的に正しいのは「I'm walking to school now」だぞ。
Comment by MortimerDongle 2 ポイント
(アメリカ合衆国)
↑現在形はいつもやってる事や日常の習慣の時に使うもので現在やってる事には使わないよ。
「I walk to school every day」と「I'm walking to school now」
Comment by greece666 2 ポイント
(ギリシャ)
英語は母国語ではないけど外国語としての英語の教師をやってる。
なぜだかギリシャ人の学生は「nowadays(最近)」って単語が大好きでどんな文にもこれを使ってる。
Comment by SnipinG1337 342 ポイント
英語ネイティブの人は時々「should of」を使うけど、ネイティブじゃない自分からするとそれ「はぁ?」って思うわ。
Comment by Elq3 147 ポイント
(イタリア)
↑僕もネイティブじゃないけどこれ気に障るわ。
僕が使うのは「should have」。「should of」は間違ってるような気がする。
Comment by MortimerDongle 96 ポイント
(アメリカ合衆国)
↑それ間違ってるんだよ。
「should of」って書く連中はそれが「should've」の響きと似ているからで実際の単語の意味とか考えてない。
「they're/there/their」や「your/you're」のように使い方を混同するのと似てる。
Comment by dragonflyspy7 2 ポイント
誰かが「such a pity!(なんてこった)」って言うと古臭いなって思う。
ドイツ人でこれを言う人間はかなり多い。
「Such a shame」や「that’s a shame」の方が普通に聞こえる。
Comment by PromoPimp 0 ポイント
多分これは既に書き込まれてるだろうけど、アメリカ英語話者ではないことが分かる決め手は「named」じゃなく「called」を使うこと。
例えば「Her boyfriend is called Trevor(彼女の彼氏の名前はTrevor)」みたいな感じで。
イギリス出身の人がこれをよく使ってる。
Comment by poluvla 343 ポイント
(セルビア)
スラヴ人はやたら冠詞を使う(overuse the articles)ってことに気付いた。
あと冠詞を間違った場所に入れたりとか。
Comment by perrrperrr 376 ポイント
(ノルウェー)
↑>>「overuse the articles」
君もそうだな。
Comment by poluvla 181 ポイント
(セルビア)
↑ああ、勿論この「the」は入れるべきではないってことは分かってたよ。
Comment by Siorac 64 ポイント
(ハンガリー)
↑これが慰めになるか分からないけど、ハンガリー語だとその文章ならそこに冠詞を入れる。
Comment by Nomekop777 5 ポイント
(アメリカ合衆国)
↑これが慰めになるか分からないけど、指摘されるまで間違ってることに気付かなかった。
言われるまで間違ってるような感じはしないよそれ。
Comment by yrnehnosliw 80 ポイント
(イギリス)
↑フランス語とロシア語を学校で習ってるけど、これ習ってると英語の冠詞の使い方が如何に複雑なものか分かる。
(フランス語だと常に冠詞を使っていて、ロシア語だと冠詞を全く使わない。英語だとそうした方が良いと感じた時にそうする)
Comment by Nomekop777 66 ポイント
(アメリカ合衆国)
↑>>「英語だとそうした方が良いと感じた時にそうする」
英語という言語がどういうものかがたったこの一文に要約されてる。
Comment by hundemuede 60 ポイント
(ドイツ)
↑面白いな。僕の彼女は英語を話すとき名称の前に必ず冠詞を入れる。「Did you see the Mike today?」みたいに。
ドイツ語だとそれをするのは普通なんだけど彼女は何故かそうしない。
Comment by Darkliandra 2 ポイント
(ドイツ)
↑高地ドイツ語からすればそれ間違ってる(勿論口語だと一般的だけど)
Comment by d3dev 3 ポイント
(ウクライナ)
ネイティブではないけど冠詞だな・・・
冠詞を正確に使うのは難し過ぎる
Comment by barbatex 3 ポイント
(イタリア)
僕の友人はロンドンで「I'm going to the seaside for the holidays(休みに海に行く)」と言って笑われてた。
Comment by See_EmilyPlay 5 ポイント
(イタリア)
↑「seaside」の代わりに何を使えばいいの?
Comment by MortimerDongle 1 ポイント
(アメリカ合衆国)
↑ここだと「beach」「shore」もしくは「ocean」
「seaside」は正しいけど実際は使われない。
Comment by xorgol 4 ポイント
(イタリア)
↑これスレの内容からは外れるけど、アメリカ人が海(sea)のことを「the ocean」って言う傾向があることに気付いたわ。
Comment by MortimerDongle 2 ポイント
(アメリカ合衆国)
↑確かにそう。
「Mediterranean/Caribbean」の正式名称以外で「sea」を使ったりはしないと思う。
(「Caribbean ocean」って表現は珍しいものでもない)
Comment by bounybeard Scotland 332 ポイント
硬い言葉と砕けた言葉をごちゃ混ぜで使うこと。
「Sir please may I have a carton of fags and these bevvies?(すみません、モクとサケを頂けますか?)」みたいな感じで。
あと単語の順序が色々とぐちゃぐちゃだったりする人がかなり多い。
Comment by Duchowicz [S] 103 ポイント
(ポーランド)
↑「whom」を使うのは?
これ学校で教わったけど時代遅れだって聞いた。
Comment by intangible-tangerine 21 ポイント
↑大半の人は硬い文章の中でしか使ってないけど、硬い文章の中でもちょっと浮いてる感じがする。
Comment by MortimerDongle 37 ポイント
(アメリカ合衆国)
↑硬い言葉と砕けた言葉をごちゃ混ぜで使うのは多い。
このサイトで文章はカッチコチに硬いのに「ain't」を入れたりする人をよく見かけるわ。
Comment by Cocan 5 ポイント
(アメリカ合衆国)
↑これと似たような感じでイギリス英語とアメリカ英語をごちゃ混ぜにするのはかなり鬱陶しい。
am not の縮約形、have not の縮約形
ain't
Comment by cuplajsu Malta 18 ポイント
(マルタ)
「like」を使いまくるのはほんとウザい。
例えそれが文法的に正しくても。
※ここでの「like」は「~のような」といった意味の方です。
Comment by Cog348 18 ポイント
(アイルランド)
↑君自分の精神のためにもアイルランドには来ない方が良い。
Comment by Lyress 2 ポイント
(アルバニア)
↑これほんとイライラする。ネイティブすら使いまくるからな。
Comment by Rybentor 14 ポイント
(フィンランド)
東欧の友達が不思議なことにやたら文中で「did」を使うってことに気が付いた。
別に強調する必要がない場合でもそうしてる。
例えば「she went to the store(彼女は店に行った)」と言うのではなくて「she did go to the store」としたり、「he baked a cake(彼はケーキを焼いた)」ではなく「he did bake a cake」としたり。
Comment by Salt-Pile 2 ポイント
(ニュージーランド)
↑これこれ!
スレ主の質問に対する返答としてはこれは完璧。
それは文法的には正しいんだけど一般的な時制の使い方からしたら古風な感じがするよね。
Comment by kashluk 2 ポイント
↑あとロシア人は訛り聴かなくても簡単に分かるぞ。あいつら「is」を使いまくるからな。
「I bought car. Is new.」みたいな感じで。
Comment by TarcFalastur 263 ポイント
これは英語が母国語の人でもあまり意識してないことなんだけど形容詞には「正しい」並び方と「間違った」並び方がある。
例えば「big, red ball(大きくて赤いボール)」は問題ないんだけど、「red, big ball(赤くて大きなボール)」だと変な風に聞こえる。
形容詞がどういう順序で並べるべきかという法則がちゃんとあるのかどうかは分からないけどうちらはこれを無意識のうちにやってる。
英語を外国語として話してる人で形容詞の並べ方が変な人はよく見かけるわ。
関連記事
「英語の形容詞を並べる順番には法則があるらしい」海外の反応
Comment by Duchowicz [S] 160 ポイント
(ポーランド)
↑形容詞の順番の法則は
・量、数
・質、意見
・大きさ
・形
・色
・適切な形容詞(国籍とか出身とか材質とか)
・目的、限定詞
>>「英語を外国語として話してる人で形容詞の並べ方が変な人はよく見かけるわ。」
それはうちらの母国語にはそんな法則はないから。少なくともポーランド語にはそんなものはない。
Comment by Siorac 21 ポイント
(ハンガリー)
↑単語の順序は他の言語にもあるよ。
ハンガリー語だと「piros nagy labda」はかなり変に聞こえるから「nagy piros labda」じゃないといけない。
(君が挙げた例と全く同じ)
Comment by Takiatlarge 11 ポイント
「You're Welcome」ではなく「Welcome」と言うこと。
ルーマニアやバルカンでこれに気付いた。
Comment by kebabelele 2 ポイント
(スウェーデン)
↑それネイティブスピーカーがやってるのよく見かける。
Comment by requiem-for-a-nong 9 ポイント
中国人は「why」の質問に「no why」で返す傾向がある・・・
Comment by fear_of_trains 213 ポイント
(アイルランド)
短縮形を使わないこと(I'm、you're、he's、she's、they're)
単語の並び方で大体その人が英語を母国語としてるかどうかが分かる。
英語母語話者であってもインド人はすぐに分かる。
インド人は「needful」とか「wrt」みたいな古風な言葉を使うから(これは19世紀の政府機関で使われていた言葉)
Comment by cleefa 4 ポイント
(アイルランド)
↑インドの人はよく「this morning」と言わずに「today morning」と言ってる。
個人的にはこれ好き!
Comment by Monomane55 3 ポイント
↑あと「ma'am」とか「sir」を使ってるのは十中八九インド人。
Comment by fear_of_trains 3 ポイント
(アイルランド)
↑もしくはテキサス人。
Comment by Bulletti 2 ポイント
(フィンランド)
↑>>「単語の並び方で大体その人が英語を母国語としてるかどうかが分かる。」
フィンランド人は特にこれが苦手。フィンランド語は単語の順番がグチャグチャでも意味は通じるから。
Comment by melissaaaflo 9 ポイント
(スコットランド)
職場のインド人とやり取りしてるときよく「kindly do the needful(お願いします)」って言われるけどこれはここイギリスじゃ全く聞かない表現。
Comment by splishsplashsploosh 8 ポイント
(イギリス)
他の動詞を使う必要がある時に「make」を使うこと。
今日俺観光客から「please make a photo of us」って頼まれた。
勿論これは酷い間違いと言うわけではないけどうちらはその場合「take」を使う。
Comment by viktor72 3 ポイント
↑逆に「to make a decision(決める)」の時に「To take a decision」にしたりな。
Comment by Ofermann 120 ポイント
(イングランド)
「サッカー板」でコメントしてる人がイギリス人のサッカーファンなのか外国人のサッカーファンなのかを見分けるやり方を知ってる。
ネイティブじゃない人やアメリカ人は「Liverpool is a football club」と書き込むんだけど、イギリスではうちらはそんな風には言わない。それだと変な感じがする。
ここでは「Liverpool are a football club」って言う。
これはアメリカ英語では集合名詞の時に「is」を使うけど、イギリス英語だと「are」を使うから。
多分ネイティブじゃない人は母国語の文法を英語にも当てはめるからそういうことが起きるんだと思う。
もしくは単にアメリカ英語を使っているか。
Comment by Malu1997 2 ポイント
(イタリア)
↑だから「the police is」と「the police are」の両方を聞くことがあるんだな。
Comment by yeahidealmemes 28 ポイント
(フィンランド)
どうもドイツ人は「this」と「that」の違いが分からないようでいつも間違ってぐちゃぐちゃに使ってる。
Comment by trinitronbxb 35 ポイント
(ドイツ)
↑母国語のドイツ語でもそれと同じ間違いをしてるドイツ人沢山いる。
Comment by Rudomekato 10 ポイント
(オーストリア)
↑これはほんとその通り。
Comment by kobakoba 6 ポイント
↑英語話すようになって20年くらいになるけど数か月前にようやくこの違いを意識するようになった。
Comment by Mar_Ci 6 ポイント
(ハンガリー)
ハンガリー人の同僚がソフトウェアについて話すときそこに冠詞をやたらつけることに気付いた。
例えば「I opened Outlook」じゃなくて「I opened the Outlook」とか。
Comment by turgid_francis 2 ポイント
(スイス)
↑ああ、ハンガリー語じゃ固有名詞と普通名詞に違いなんてないからな。
Comment by intangible-tangerine 67 ポイント
'Hello how are you?'
'I'm fine thank you'
このやり取りを聞けばその人が学校の教科書と英語教師から英語を学んだってことが分かる。
Comment by FizzyCent 6 ポイント
「Practice makes it better.」
多分ネイティブスピーカーだったら「Practice makes perfect.(努力は実を結ぶ)」って言うと思う。
間違ってるわけじゃなくて、単にそう思うってだけ。
Comment by NiqPat 6 ポイント
(ブルガリア)
そんなことより「could care less」とかほざく連中は死刑にすべき。
Comment by SelaZela 4 ポイント
(スウェーデン)
↑それには同意するけど、それ言ってる連中の大半はネイティブスピーカーなんだよね。
Comment by Jaraxo 46 ポイント
「Quid」はポンド通貨を意味するスラング。
「I won 50 quid last nigh」だと「昨晩50ポンド当たった」って意味になる。
ただこれは「Sheep」のように常に単数形で使う。
時々「quids」って言ってる人を見かける。
Comment by Siorac 26 ポイント
(ハンガリー)
↑それは筋が通ってないってことをお前らは認めるべき。
「fifty pounds」なのに何で「fifty quids」じゃないんだよ?
イギリス人からこの事はさんざん聞いたけど未だに筋が通ってないと思うわ。
このOEDでsheepという単語を引いてみますと、「先史時代には複数形であることを示す語尾として-uが付いていたと考えられるが、古英語(700年頃~1100年頃の英語)の時代にはその語尾-uが脱落して、単数形と複数形が同形になった」と英語で説明されています。古英語の名詞には、ドイツ語と同じように、男性名詞・女性名詞・中性名詞という区別があり、sheepは中性名詞に属していました。そして、sheepのように長い母音も持つ中性名詞は、複数であることを示す語尾-uが脱落して、単数形と複数形が同形になったのです。
第25号:sheep(羊)の複数形は なぜそのままsheepなのでしょう?
Comment by Ofermann 119 ポイント
(イングランド)
フランス人が自分たちのことを言う時「as a French」っていうのは「正しい」英語ではない。
けどある程度の人がずっと言い続けてたらそれが正しいってことになると思う。
「正しい」言い方は「as a Frenchman」もしくは「as a Frenchwoman」
Comment by KirbyWarrior12 6 ポイント
(イングランド)
↑これ中国人がやってるのをよく見かける。
中国政治や文化に関する動画じゃ半分くらいのコメントが「I am a Chinese and...」から始まってる。
Comment by x1rom 1 ポイント
(ドイツ)
↑「as a France」って表現もかなり沢山聞いたことがある。
Comment by JoMiner_456 279 ポイント
(ドイツ)
俺は「mobile(携帯電話)」ではなく「handy」を使ってしまってる。
こっちの単語の方が慣れてるから。
Comment by Scottish_Man 63 ポイント
(スコットランド)
↑ドイツ語の授業で先生がドイツ語では携帯電話のことを「handy」って言うと言った時僕や友達は爆笑してそれから他に人も笑い始めた。
思春期特有のガキっぽさではあるけどここスコットランドでは「handy」は手でピーーするという意味のスラングだからこれが一緒に使われてるのはヤバい 😂
Comment by TheLizardKing89 3 ポイント
↑ここアメリカ合衆国でもそう。
Comment by itsredditoclock 474 ポイント
(アイルランド)
「I'm」じゃなくて「I am」を使ってるのにはちょっと固まる。
「I am going to the shop」とか「I am studying english」みたいな感じで。
英語のネイティブスピーカーは強調したい時なんかには時々「I am」を使ったりするけど、変な感じがするからこれを別々にすることはまずない。
Comment by bledin2 in 268 ポイント
(スロバキア)
↑僕がそうするのはキーボードのせい。「'」が何処にあるのかいつも忘れるから。
Comment by intangible-tangerine 60 ポイント
↑若い人は初めて短縮を習うとやたらと使う。
「He is taller than I'm」とか。
Comment by itsredditoclock in 21 ポイント
(アイルランド)
↑そんなの今まで聞いたことない!
Comment by Ercarret 11 ポイント
(スウェーデン)
↑それって文法的に間違ってるの?それとも変な感じがするだけ?
Comment by PeterPawlettsBaby 37 ポイント
(スコットランド)
↑基本的に文章中の主語で使われるもので目的語としては使われない。
だから「She's taller than I am」とか「I'm taller than she is」なら良いけどその逆はない。
Comment by lokaler_datentraeger 53 ポイント
(ドイツ)
↑「she isn't」と「she's not」って意味違うの?
Comment by crackanape 30 ポイント
(オランダ)
↑ぼくからすると「she’s not」だと彼女がそれをしないことを強調してるように感じする。
「She isn’t going.」:ああ、多分彼女は今週忙しいんだろうな。
「She’s not going.」:彼女はそこに行くのが嫌で、頼んだとしても無理。