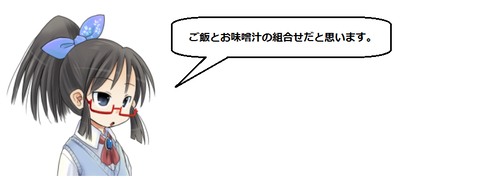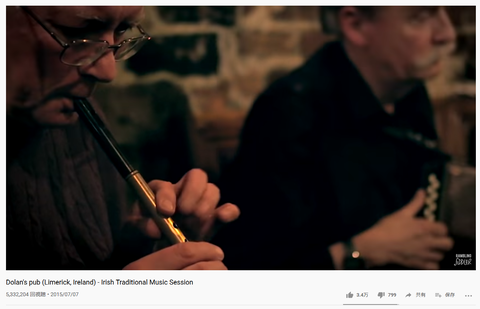Comment by Jett728
(アメリカ合衆国)
君達の国の文化で決してなくなったりしないであろうものって何?
何世代経っても文化として残り続けるような感じのやつ。
reddit.com/r/AskEurope/comments/gn6fi8/what_is_a_part_of_your_culture_that_will_never/
Comment by nexustron 613 ポイント
(フィンランド)
これは間違いなくサウナ。
世界的にもサウナの人気が高まっているんだからフィンランドでのサウナ人気が衰えるとは思えない。
Comment by Dr__Noonian__Soong 88 ポイント
↑アメリカ人だけど夫と一緒に私達の古い燻製用の小屋をサウナに変えて、ドアにはフィンランドの国旗を描いた!
ウィスコンシン州やミネソタ州にはフィンランドの入植者が多かったからサウナが多い。でも東海岸にはない。
Comment by Eatmykebab 6 ポイント
(イギリス)
↑コロナのせいで今後数年間サウナ人気は衰えるかもしれんよ。
Comment by nexustron 83 ポイント
(フィンランド)
↑そうかな?大半の人の家にはサウナがあるから外に出る必要ないし。
Comment by chazskellon 3 ポイント
(イギリス)
フランス人、スコットランド人、ウェールズ人、アイルランド人との愛憎入り混じった関係性。
Comment by Monrai Ukraine 4 ポイント
(ウクライナ)
多分サーロじゃないかな?
ウクライナ人がこれを食べなくなるようになるとは思えない。
サーロ(ウクライナ語:сало / salo)は、ウクライナ料理で供される、豚の脂身の塩漬けである。「白豚脂」と意訳される。食用油脂のラードと異なり、未精製で食される。ボルシチとヴァレーヌィクと並んで、ウクライナの代表的な伝統料理である。
サーロ
Comment by Seveand 489 ポイント
(ハンガリー)
自家製アルコール。
庭で果物を育てている人はみんなそれで酒を作ってワインやスピリッツにする。
どの家庭も自分たちのワインや「パーリンカ(アルコール度数60度以上のスピリッツ)」の美味しさを誇りに思っていてそれを飲みたがる人にあげてる。
もし君がハンガリーを訪れたなら渡されたパーリンカは断らないようにした方が良い。これが俺達ハンガリー人の知らない人に対するホスピタリティだから。
Comment by Eric-The_Viking 101 ポイント
(ドイツ)
↑そしてそれはすぐに「hospitalized(入院する)」方法でもあるな。
Comment by Seveand 81 ポイント
(ハンガリー)
↑うちらはお互いにお互いのことを見てるから入院まで行くことは珍しいけど、真っ直ぐ歩けなくなるくらいまで飲むのは珍しい事じゃない。
Comment by JustAnonymWolf 93 ポイント
(ルーマニア)
↑それはうちらもそうだと思う。
それと自家製のソーセージとかも。これ最高。
Comment by m_roofs 39 ポイント
↑職場でハンガリー人の同僚から誕生日に自家製パーリンカを贈られたことがある。
仕事が終わってすぐに貰ったんだけど10分でほろ酔いになった。
Comment by Seveand 37 ポイント
(ハンガリー)
↑不意打ちのパーリンカの衝撃ってのはトラック以上だからな。
Comment by ItsACaragor 31 ポイント
(フランス)
↑フランスの田舎だとそれかなり一般的。どの家庭も自家製の「eau de vie」を持っていて食後に出される。
パーリンカ(ハンガリー語:pálinka['paːliŋkɒ])は、ハンガリーで造られる、果物を原料とする蒸留酒である。なお、ハンガリー国外で造られる同様の蒸留酒はパーリンカを名乗ることはできず、フルーツブランデー、ツイカ、ラキヤなどと区別される。語源はスロバキア語で「燃やす(蒸留する)」を意味する「pálenka['paːlɛŋka]」、さらに基はスラヴ語の「páliť」から。
素材として使われるフルーツは様々なものがあるが、最も一般的なものはプラムで、次いでリンゴ、洋ナシ、チェリー、アプリコットなどがある。
パーリンカ
「オー・ド・ヴィー(Eaux-de vie)」とは、フランスにおけるブランデーをはじめとする蒸留酒の総称です。
ラテン語で「生命の水」を意味する「アクアヴィテ」を語源とすると言われています。
オー・ド・ヴィー -Eaux-de vie
Comment by Flanker1971 6 ポイント
(オランダ)
子供にアイススケートを学ばせること。
たとえ何年もちゃんとした天然の氷がなかったとしてもこれは無くならない。
次の「Elfstedentocht」に備えないと。ひょっとしたら来年かな?
11都市スケートマラソン「エルフステーデントホト」は、世界最大のスケートマラソンです。その参加者数は15,000人、そして全国から大勢のファンが応援に駆けつけます。会場は、フリースランド州の11都市を結ぶ全200キロの水路。コース全体に厚い氷が張る厳冬にだけ開催される、幻のスケートマラソン大会です。
1890年、百人余りの男女がフリースランド州の町をスケートで1日で走破しようと試みたことがきっかけで、このスケートイベントは誕生しました。以来、11都市スケートマラソンは15回開催されています。前回の開催は1997年。その時に世紀の大イベントを見ようと世界中から集まった観衆は200万人、世界各国のメディアスタッフは約2千人でした。
11都市スケートマラソン
Comment by Havajos_ 4 ポイント
(スペイン)
内輪揉めとゆるいライフスタイル(酒を沢山飲んでシエスタで寝ること)
Comment by gerginborisov 403 ポイント
(ブルガリア)
聖名祝日。
アメリカ合衆国に遠戚の従兄弟(移民三世代目)が何人かいるんだけど、従兄弟たちはほとんどブルガリア語話せない。
でも聖名祝日のことは今でも祝ってる。
Comment by DeadPengwin 143 ポイント
(ドイツ)
↑面白いな。僕の祖父は第二次世界大戦前に育ったんだけど当時は誕生日よりも聖名祝日の方が祝われていたって言ってて変なのって感じたことがある。
僕が子供の頃は聖名祝日でちょっとしたプレゼントは貰ってたけどパーティーとかそういうのはしてなかった。
Comment by knightriderin 11 ポイント
(ドイツ)
↑それはギリシャでもそう。
ギリシャ人の血が流れていてドイツに住んでいる友人がいるけど、そいつは誕生日をドイツ人の友人たちと祝って、聖名祝日は家族で祝ってる。
Comment by EmiSflake 5 ポイント
(ブルガリア)
↑その通りだと思う。誕生日よりも聖名祝日を祝うことの方が大半だしね。
Comment by Im_George_ 2 ポイント
(ハンガリー)
↑それはここハンガリーでもそう。
聖名祝日(せいめいしゅくじつ)は、キリスト教における聖人の記憶日である。
非キリスト教圏ではなじみが薄いが、聖名祝日は国によっては子供の名前をつける際の重要な要素となる。誕生日の聖人から洗礼名をいただくほか、誕生日の聖人を個人の守護聖人としたり、洗礼名をいただいた守護聖人を個人の守護聖人としたり、あるいはその複数をおこなったりする習慣が広く存在する。自分の洗礼名の聖名祝日や守護聖人の聖名祝日を、自分の誕生日と同等もしくはそれ以上に祝う風習のある国もある(ただし、それらの日付は一致することもある)。
聖名祝日
Comment by ansanttos 3 ポイント
外国と対戦する時に家族や友人と一緒にカフェでポルトガルのサッカーチームを観戦することはポルトガルではなくなることはない。
Comment by ThatMakesMeTheWinner 2 ポイント
イギリスの場合は上品なアクセントの人に対する盲目的な敬意。
全員がそうだというわけじゃないけど、こういう人がまだかなり多い。
Comment by kpagcha 250 ポイント
(スペイン)
多分のんびりとした文化。
俺達が計画通りに物事を進めるようになったり、時間通りにしないといけないことを理解したりすることはないだろうし、どうでも良いことに力を注いだりすることもないはず。
俺達は「ゆったり」とした時間の方を大事にするから。
あとタパス文化。
Comment by mkulinsky1 43 ポイント
(ポーランド)
↑人が遅刻するの嫌いだけど、多分それは自分がドイツ近くに住んでいるポーランド人だからなんだと思う。
Comment by amunozo1 69 ポイント
(スペイン)
↑俺も人が遅れるのは好きじゃないよ。人に対する礼儀に欠けてる。
何で自分の「ゆったり」とした時間を他人を待つことで潰さないといけないんだ?
Comment by ahsurebegrandlad 39 ポイント
(アイルランド)
↑大学でスペイン人と一緒に生活してたけど、彼の人生をのんびりと生きるやり方は羨ましくもあり、怠け者すぎるのがイライラしたりもした。
Comment by somememberofmankind 38 ポイント
(ギリシャ)
↑ギリシャもそう。多分これ地中海あるあるなんだと思うw
タパスまたはタパ(スペイン語単数形 Tapa)とは、スペイン料理の様々なアペタイザーである。冷製料理(オリーブとチーズ混ぜ合わせ等)または温製料理(小イカフライ等)がある。
タパスは小皿料理なので、会話をしながら食事をするのに向いている。また、タパスを立食とする習慣がある国もある。スペインではバルによって無料で出すところもあり、店によって、さまざまなものがある。
タパス
Comment by European_Bitch 222 ポイント
(フランス)
アルコール、愚痴、最終的には口論になる家族の夕食。
Comment by Fandechichoune 6 ポイント
(フランス)
↑うちらの国じゃこの数十年でアルコール消費量はかなり落ちてるぞ。特にワイン。
Comment by EntopticVisions 160 ポイント
(アイルランド)
音楽。うちらアイルランドは音楽に関しては実に実り豊かな国。
コロナの後戻ってきてほしいと思っているのはパブセッション。
これはギターやフィドル、アコーディオン、ティン・ホイッスル、フルートの演奏家がパブで集まって演奏するものでとても楽しい。
Comment by Acc87 52 ポイント
(ドイツ)
↑コロナがあってもパブ文化は残ってほしいな。
二か月くらいになるけど既に好きなパブが二件閉店してしまった。
パブ・セッション(英: pub session、アイルランド語: seisiún、マン島語:seshoon)は、各地のパブのくつろいで打ち解けた舞台での音楽演奏や歌唱を指し、そこで生まれる音楽はエールやスタウト、ビールの消費や会話と混じりあう。ミュージシャンたちは、アイルランド、イングランド、スコットランド、マン島の伝統的な歌やチューンを歌い奏でる。
楽器としては主に、フィドル、アコーディオン、コンサーティーナ、フルート、ティン・ホイッスル、イリアン・パイプス、テナーバンジョー、ギター、バウロンが使われる。
パブ・セッション
https://www.youtube.com/watch?v=O9a8pVGa1Mo
Comment by DG_Insomniac 159 ポイント
(ルーマニア)
アルコール中毒、バーベキュー、愚痴。
これが無いルーマニアなんて想像できない。
Comment by Syrob 80 ポイント
(ポーランド)
↑ポーランドに来てみると良い。まるで自宅にいるような気分がするはずだから。
Comment by Tramagust 70 ポイント
(ルーマニア)
↑彼女がポーランド人だけどルーマニアは古代ローマをスラブ風にリミックスしたような感じだっていつも言ってる。
Comment by molten07 145 ポイント
(トルコ)
紅茶好き。
トルコ出身であればどんな民族、宗教、言語だろうとリラックスして家族や友人と茶を満喫する。
Comment by mkulinsky1 1 ポイント
(ポーランド)
↑トルコのことは知らないけど紅茶に牛乳入れるのはどう思われる?
ポーランドじゃそんなことをする人間は誰もいなくて、化け物か何かだと思われる。
牛乳が入っているの紅茶が好きなだけなのに :(
Comment by Radioactive_Hedgehog 5 ポイント
(トルコ)
↑大半の人は紅茶に牛乳を入れるなんて聞いたことがないと思う。
君狂人扱いされるよ。
Comment by asicomeinpeace 75 ポイント
(オランダ)
国王の日
たとえ君主制がなくなって祝日の名称が変わったとしてもみんなオレンジ色になってパーティーをし続けると思う。
楽しい日だからこれが無くなるなんて想像が出来ない(今年はコロナのせいでなくなったけど)
Comment by snedertheold 37 ポイント
(オランダ)
↑それ要するに酒を飲む別の口実だろ。
国王誕生日(こくおうたんじょうび)は、オランダ国王の誕生を祝う、オランダの祭日である。オランダ語では Koningsdag。直訳で王の日(おうのひ)または国王の日とも言う。オランダの国家の日とされている。
この日にはオランダ全土がオレンジ色(オランダ王家の色)の飾りが掲げられ、さまざまなパレードや音楽祭が催されるほか、 vrijmarkt(フリーマーケット)が開かれ、街の通りで住人が自由に物を売買することが許されている。
国王誕生日 (オランダ)
Comment by TMCThomas 47 ポイント
(オランダ)
花火とシンタクラースの文化は残り続けてほしいけど、年々大丈夫か心配になってきてる。
Comment by The_real_tinky-winky 29 ポイント
(オランダ)
↑花火はそのうち無くなりそうだと思うけど、シンタクラースは大丈夫でしょ。
なくなるとしたらズワルトピートの方。
関連記事
オランダ「伝統的な聖人の従者が人種差別だと叩かれる風潮は何故なのか」海外の反応
日本では、場所を選べば夏以外の時期も花火をして問題ありませんが、オランダでは普段は花火は禁止されています。
花火の販売に関してもルールがあります。花火を購入するには、12歳以上である必要があり、種類により18歳以上となります。最低年齢は花火の種類によって異なります。販売期間は3日間。2019年は28日、30日、31日です。販売元には販売のライセンスもあるようです。
オランダの大晦日・新年の花火に要注意!
シンタクラース(オランダ語: Sinterklaas)またはシント=ニコーラース(蘭: Sint-Nicolaas)はオランダの神話的存在である。ミラのニコラオスに基づく伝説的、歴史的な存在で民間伝承に起源をもつ。
クリスマスの象徴であるサンタクロースは主にシンタクラースを原形にしている。
ズワルトピート(オランダ語: Zwarte Piet、「黒いピート」の意味、複数形は Zwarte Pieten ズワルトピーテン)はシンタクラースの侍従で、16世紀の貴族の衣装に基づく服を着ている。しばしばレースの襟と羽飾りのついた帽子で飾り立てている。
伝統的にズワルトピートはスペインから来たムーア人だから顔が黒いのだといわれる。今日では、煙突をくぐってススが付いたから黒いのだという説明のほうが好まれる。ズワルトピートの外見が人種差別だと受け止められることがある。 この例のように、シンタクラースの祝日をめぐる伝統は、数多くの論評、批評、議論、ドキュメンタリー、抗議、ときには祭りの中での暴力的衝突の種にすらなった。
とはいえ、ズワルトピートとシンタクラースの祭りは、今日でもオランダでは支持が厚い。2013年の世論調査では、オランダ人の92%がズワルトピートを人種差別または奴隷制度と関連があるとは考えないとし、また91%がズワルトピートの見た目を変更することに反対と答えた。
シンタクラース
Comment by Brainwheeze 13 ポイント
(ポルトガル)
コーヒー。
朝と昼食の後にコーヒーを飲むのはもはや儀式だから大半のポルトガル人はこれ無しで外には行けない(自分もそう)
ときどきカフェの近くでやたら乱暴な駐車をしてる車を見かけることがあるけど、運転手がコーヒーを飲みに行ったんだなって察しが付く。
Comment by tobuno 3 ポイント
Teaching young boys to ceremoniously whip women and splash water at them every easter. https://www.welcometobratislava.eu/traditional-easter-in-slovakia/
You usually phase out of it as an adult man nowadays, thinking how horrible it is, yet you refuse to not pass on the experience to the kids. :)
(スロバキア)
毎年イースターに女性を儀礼的に鞭打って水をぶっかけるようにと若い男性に教える事。
https://www.welcometobratislava.eu/traditional-easter-in-slovakia/


最近だと成人男性はこれはヤバいだろって考えてやらなくなっていってるけど、これを子供に伝えること自体はやってる。
Comment by Mywonderwall 3 ポイント
(スウェーデン)
フィーカ。
https://sweden.se/culture-traditions/fika/
これが無くなりでもしたら暴動が起きる。
職場だろうと、友人と街に居ようと家族と自宅に居ようと俺達はフィーカタイムを過ごすから。
フィーカ(典: fika)はスウェーデン語の動詞および名詞であり、大まかな意味は、通常甘いものと一緒に「コーヒーを飲む」ことである。より新しい用法では、子供達がコーヒーの代わりにお茶、レモネード、スカッシュを飲むこともフィーカに含まれるようになった。
フィーカはスウェーデンの生活慣習であり、休憩をとること、主として同僚、友人、恋人または家族とコーヒーを飲む時間を意味する。「fika」という単語は動詞または名詞として使われる。スウェーデンではコーヒーを飲むことが重要な文化であると考えられている。「コーヒーブレイク」をとることで仕事中にフィーカしたり、「コーヒーデート」のように誰かとフィーカしたり、単に1杯のコーヒーを飲むこともできる。
フィーカ
Comment by ElectricalInflation 2 ポイント
(イギリス)
天候のことなんてどうでも良いと考えているのに天候について愚痴を言うこと
Comment by EUGENIA25 30 ポイント
(イタリア)
マフィア。
これは自分の文化じゃないけど、作家のレオナルド・シャーシャが昔「シチリア人が二人存在する限りマフィアが無くなることはない」って言ってた。
レオナルド・シャーシャ(Leonardo Sciascia, 1921年1月8日ラカルムート - 1989年11月20日パレルモ)は20世紀のイタリアの作家、小説家、詩人、評論家、政治家。イタリア文学史上初のマフィアを告発する小説を書いた作家として知られる。しかしマフィア問題はシャーシャが扱う多くの社会問題の一つに過ぎず、作家のテーマは「人間の威厳(Dignità dell'uomo)」と「正義(giustizia)」である。
レオナルド・シャーシャ
Comment by wurzlsep 19 ポイント
(オーストリア)
「sudern(=あらゆることに文句を言うこと)」の文化
Comment by amazingstarwars321 212 ポイント
(オランダ)
天候に文句を言うこと。
夏になると暑すぎると言い、冬になると寒すぎると言い、どの季節も気候が多すぎると文句を言う。
うちらオランダ人が天候に満足することはない。
Comment by punkisnotded 96 ポイント
(オランダ)
↑「気候が多すぎる」って部分ほんと好き。何でかってうちらの気候は穏やかな気候だから。
Comment by Popka_Akoola 3 ポイント
↑何でどの文化圏でも一番文句を言うのが天候についてなんだ?
僕はアメリカ合衆国中西部の出身だけど、それうちらのことを完璧に紹介してるよ。
Comment by thebelgianguy94 10 ポイント
(ベルギー)
税金について文句を言うこととか?
ベルギー人は税金を受け取っていないテレビ局に対してすら「俺達の税金でこんなクソみたいな番組作ってやがる」って叩いてる。
Comment by Lecno_New 41 ポイント
(クロアチア)
貧乏な状態で、自分では何かを変えようとせず文句を言うこと。
Comment by vox_verae 16 ポイント
(スロバキア)
↑スロバキアのことが書かれてるのかな?
Comment by Beeblebrox237 216 ポイント
(イギリス)
パブに行く事。
パブ文化は時代によって変わってるけど、それが無くなることはないと思う。
次の世代には次のやり方があるってだけで。
Comment by Gloob_Patrol 3 ポイント
(イギリス)
↑イギリスの職場はどこもその月の最初の木曜日の仕事終わりに行く非公式のパブクラブがある。
これは宗教。
Comment by xull_the-rich 5 ポイント
多分アイリッシュダンス。
偉大なアイリッシュダンサーの多くはアイルランド出身じゃない。
例えばマイケル・フラットレーとか。
マイケル・フラットレー(Michael Ryan Flatley、1958年7月16日 - )は、アイリッシュダンスのダンサー、振付師である。アイルランド系米国人。
リバーダンスの振付師、初代リードダンサーとして有名。
1秒間に35回タップをする事ができ、世界一早くタップを鳴らせる人物としてギネスにも記載された。
彼の両足には2500万ポンド(日本円にして約32億5000万円)の保険がかけられていた。
マイケル・フラットレー
Comment by Swedishboy360 6 ポイント
(スウェーデン)
うちらスウェーデン人と他のスカンジナビア人の間での冗談のやり取り。
千年後スウェーデン人が別の太陽系のスペースステーションにいたとしても100%間違いなくデンマーク人についてのジョークを言い続けているはず。
Comment by DeadPengwin 189 ポイント
(ドイツ)
これは簡単。ビールとサッカー。
この二つはドイツの文化に根深く染み込んでいるからそうそうこれがなくなったりすることはないはず。
Comment by Acc87 52 ポイント
(ドイツ)
↑サッカーは・・・国際試合だったらそう。みんなワールドカップやユーロカップの時は話題にしてる。
でもブンデスリーガレベルではそんなことはない。
Comment by DeadPengwin 49 ポイント
(ドイツ)
↑スレ主は全員にとってそうでないといけないとは言ってないだろ。
俺はサッカー見ないけどそれがドイツ文化に染み込んでいることは否定できない。国家レベルでそうだから。
ドイツにおけるサッカー・ブンデスリーガ(ドイツ語: Fußball-Bundesliga フースバル・ブンデスリーガ、サッカー連邦リーグ)は、ドイツのプロサッカーリーグである。1部、2部それぞれ18クラブ、3部20クラブの合計56クラブが所属している。観客動員数では世界第1位のプロサッカーリーグである。
サッカー・ブンデスリーガ (ドイツ)