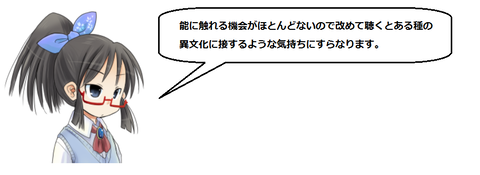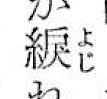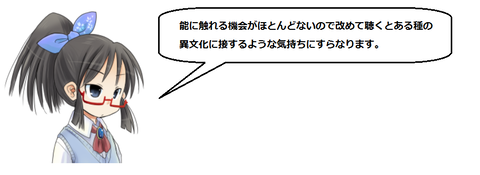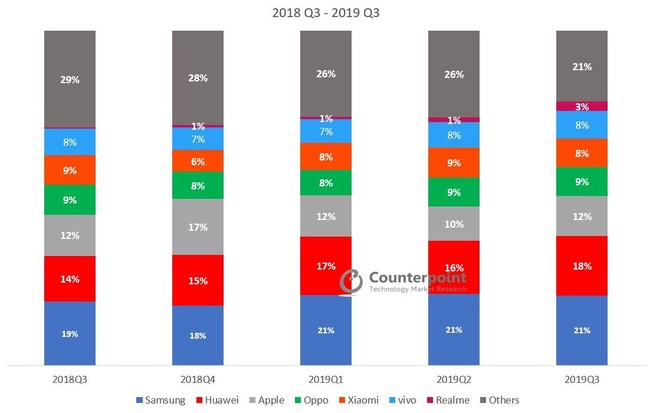こちらは日本郵船の社員だった正木照蔵が明治33年(1900年)に欧米各国を訪れたときの旅行記(『漫遊雑録』)で、興味深かった記述や当時の社会の様子が窺える記述を取り上げた記事です。
なお、引用箇所の一部には現代の基準だとあまり良くない表現がある場合もありますが、歴史的記述であることを尊重し一切手を加えていません。
<正木照蔵>
1862-1924 明治-大正時代の政治家。
文久2年7月生まれ。兵庫県会議員,報知新聞記者をへて日本郵船に入社,外航課長などをつとめる。大正6年衆議院議員(当選2回,憲政会)。
正木照蔵
参考文献:正木照蔵 『漫遊雑録』 1901年 正木照蔵
関連記事
【宣伝】暇劇の同人誌(『幕末・明治期の西洋人が見た日本(絵画篇)』)が完成しました。【宣伝】暇劇の同人誌第二弾(『幕末・明治期の西洋人が見た日本(入浴文化篇)』)が完成しました。[PR] 暇は無味無臭の劇薬のYouTubeチャンネル
●日本と西洋の歌についての記述です。
社長と川田氏とは豫て觀世流の謡曲に堪能なれば一夕其中に加りて二人にて松風の一節を謡へり、
全く西洋の樂譜とは流違ひ、調子違ひの謡曲なれば、其聲(こえ)の抑揚高低、彼等の耳には變(へん)に聞ゆると見え彼處の隅、此處の隅よりクス々々と笑聲漏れ出し中にも二三の婦人達は手巾(ハンカチ)にて顔を覆ひ、禁ゑ兼たる様なりしも可笑かりき、是れ固(もと)より謡ふ者の罪にあらず、聽く者の解さざるに因るのみ
例へば我邦人が始めて西洋人の謡ふ聲を聞き犬の遠吠に似たりと評し去りたると一般なり
正木照蔵 『漫遊雑録』 1901年 正木照蔵 p.10
【要約】
船の中で開催された音楽会で、正木照蔵の同行者である日本郵船会社の社長の近藤廉平と社員の川田氏の二人が能の「松風」を歌ったところ、日本の歌に慣れていない西洋人には変に聞こえて笑い声が起きたことについて、正木照蔵がこれは聞く者が慣れていないためであるとして日本人が初めて西欧人の歌声を聞いたときに「犬の遠吠えのようだ」と思ったことを紹介しています。
【備考】
能については知識がなく「松風」がどういう作品なのか詳しく知らなかったのですが、在原行平の歌を元にした作品とのことです。
この作品は、もともと田楽の役者である喜阿弥(きあみ:亀阿弥とも)が作った「汐汲」という能を、観阿弥が「松風村雨」という曲に改作したものを、世阿弥がさらに手を入れた秋の季節曲です。昔から、「熊野(ゆや)松風は(に)米の飯」(三度のご飯と同じくらい飽きのこないことのたとえ)と言われるほどで、春の季節曲である熊野と並び、非常に高い人気があります。
松風(まつかぜ)
※関連動画
 https://www.youtube.com/watch?v=BV_k08xkOfE
https://www.youtube.com/watch?v=BV_k08xkOfE 真剣に歌っている人を笑うという記述は読んでいてあまり気持ちの良いものではありませんが、能を全く聞いたことがない西洋人がいきなりこれを聞いて思わず笑ってしまうというのもある程度は理解できますし、これは西洋人に限ったことではなく、西洋人の歌を初めて聞いた当時の日本人も同じように大笑いしたという記述を見かけます。
例えばバジル・ホール・チェンバレンは「日本事物誌2」の中でイタリアの歌劇団が日本で公演をした時の様子について次のように記述しています。
ところが、日本の観客に与えた驚きは大変なものであった!彼らが一度ショックから立ち直ったとき、プリマドンナ(主役女性歌手)の歌う甲高い声を聞いて、わっと爆笑した。彼女は実際は決して下手ではなかったのだ。人びとは腹の皮が○(よじ)れ、涙が頬を伝って落ちるまで、ヨーロッパ人の歌い方の馬鹿馬鹿しさを笑った。彼らは袖で口を隠し(われわれならばハンケチで口を押えるところだが)、無理に笑いを耐えようとした。もちろん、このような試み[歌劇公演]は繰り返されることはなかった。
バジル・ホール・チェンバレン 『日本事物誌2』 1974年 平凡社 p.254
※「○(よじ)れ」の部分は「捩れ」ではなく以下のような漢字でした。IMEパッドで手書き入力したところ一番近い漢字は「綟」でしたが細かい部分が違っているので、ここでは「○(よじ)れ」と表記しています。
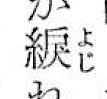
どちらに対しても歌が笑われたことについては気の毒に思ってしまいますが、当時まだ西洋と日本の歌がお互いに全く異質な物だった中では「笑う」というのがお互いに対する正直な反応だったのかもしれません。
記述の後半での西洋人の歌が「犬の遠吠に似たり」という日本人の感想も実に素直すぎる感想で思わず微笑してしまったのですが、おそらくこれは日本人が西洋のオペラを初めて聞いた時の感想なのでそのような感想も十分理解できる範疇ではないかと思います。
なお、このようなことは歌に限ったことではなく演劇に関しても同様で、明治14年(1881年)に来日したフランス人のエドモン・コトーは日本の芝居について西洋人の視点から次のように言及しています。
不自然な所作、悲劇的場面においてとる捩れた姿勢等々は他国では爆笑をひき起こしかねないが、日本の観衆はこれを眺め言葉に聞き入ってあきることがない。彼らの眼からみれば普通の人のように振舞わないことこそが、主人公の主人公たるゆえんらしい。
エドモン・コトー 『ボンジュールジャポン 青い目の見た文明開化』 1992年 新評論 pp.130-131
尤も、馴染みがなかった音楽について全く理解できなかったという記述ばかりでもなく、1912年発刊の「巴里絵日記」などでは日本画家の橋本邦助がオペラ鑑賞の際、慣れていない西洋音楽について次のように言及している箇所があります。
西洋の音樂らしき音を聞く經驗の少ない僕には、實に珍らしく咸じた。ホリベルジヱーや、ムーランムージのドンガラ、ピーピーの音樂とは非常な差だ、僕は唯譯もなくうれしく咸じた。
歌劇が始まつたが、僕には何が何だかさつぱりわからない。しかし男も女も、音聲の立派なのには聞き惚れる。
橋本邦助 『巴里絵日記』 1912年 博文館 pp.116-117
慣れていない西洋音楽についてこのような感想を持っていた日本人は当時の文献を読んでいてもなかなかいないので、この記述を読んだ時、かなり柔軟な感性を持っていた人なのではないかと率直に感じました。