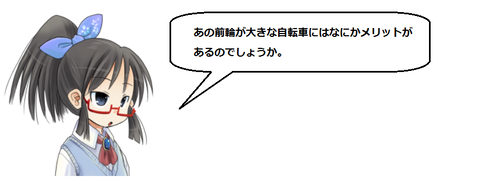「神様に与えられた呼吸を奪うのか」、マスク義務化に断固反対のアメリカ市民米フロリダ州パームビーチ郡では、新型コロナウイルスの流行対策として、公共の場でのマスク着用を義務化する法案の採決の前に、委員会が市民の意見を聞く機会を設けた。反対を唱える市民からは、マスク義務化は悪魔の法律だという意見や、共産主義の独裁体制だ、アメリカ国旗に対する侮辱だといった意見が聞かれた。続く↓

Just another WordPress site
スレッド「ぬいぐるみ無しでは家を出ない犬の写真をまとめてみた」より。海外サイトで話題となったゴールデンレトリバーのポイちゃんの画像と反応をまとめました。
引用:Boredpanda
image credit:youtube.com
こちらは明治時代の官僚だった松井茂が官命によって明治34年(1901年)から明治35年(1902年)にかけて欧米各国の警察制度を視察したときの視察記(『欧米警察見聞録』)で、興味深かった記述や当時の社会の様子が窺える記述を取り上げた記事です。関連記事
なお、引用箇所の一部には現代の基準だとあまり良くない表現がある場合もありますが、歴史的記述であることを尊重し一切手を加えていません。
<松井茂>
松井 茂(まつい しげる、1866年11月4日(慶応2年9月27日) - 1945年(昭和20年)9月9日)は、日本の内務官僚、政治家。
1901年から翌年まで欧米各国を巡歴し警察及び消防を視察、救助はしご車の輸入や救急自動車の導入に尽力する等、日本に於ける警察と消防行政の基礎を築いた人物である。
松井茂
参考文献:松井茂 『欧米警察見聞録』 1909年 警察協会
伯林(ベルリン)に於ては自轉車(じてんしゃ)の届出者は九萬(まん)人許(ばか)りもあり、又凡ての乗手は乗車券(Fahrkarte)を有すべきものである、
(中略)
千九百年に於て新たに許可を與(あた)へたる者は、六萬九千八百六十三人にして、千九百一年に於ては、七萬二千百八十六人である、尚此免許證は毎年一度與へるとの事である。
松井茂 『欧米警察見聞録』 1909年 警察協会 pp.71-72


本邦に於てハ未だ英佛等の如く自轉車學校及び練習所の設けあらざるなり
自轉車學校に入りて之を學バずとも少しく忍耐して朝夕一二時間つつ勉强すれバ凡一週間乃至三週間にて自由に乘り得るに至るべし
金澤来藏 『自轉車利用論 乗方指南』 1890年 金澤来藏 p.82

尋常の人は大抵三時間を經ば能く自轉車に慣るることを得るなり
嚶々亭主人 『少年教育遊戯』 1895年 求光閣 p.64
東京にて自轉車の流行は廿五年秋冬の交に弗々其頭角を顯はし、一昨年(廿六年)來俄に其數数増加し近來に至りては東京市のみならず、京都、大坂、神戸等の各地方にも傳播し、今や大流行を極むるに至り
社会叢書第3巻 『娯楽倶楽部』 1895年 民友社 p.48
洋式自轉車の、始めて我國に入りしは、明治十四五年頃印刷局へ三輪車の輸入あり、
二十二三年より追々流行となれり。されども、三十年ころまでは、實用よりは、寧ろ娛樂用のもののみ多かりし。
石井研堂 『明治事物起原』 1908年 橋南堂 p.227
近頃電報配達が自轉車に乘りて電文を配達することを始めたりこの電報配達に関しては先日紹介した井口丑二の「世界一周実記」の記事でも少し取り上げていますのでご興味のある方はご覧ください。
嚶々亭主人 『少年教育遊戯』 1895年 求光閣 p.66