
韓国のネット掲示板イルベに「大韓民国の全盛期時代」というスレッドが立っていたのでご紹介。 続きを読む

Just another WordPress site
スレッド「誰よりも酷い一日を過ごした人達を集めてみた」より。
引用:Boredpanda
こちらは明治時代の官僚だった松井茂が官命によって明治34年(1901年)から明治35年(1902年)にかけて欧米各国の警察制度を視察したときの視察記(『欧米警察見聞録』)で、興味深かった記述や当時の社会の様子が窺える記述を取り上げた記事です。関連記事
なお、引用箇所の一部には現代の基準だとあまり良くない表現がある場合もありますが、歴史的記述であることを尊重し一切手を加えていません。
<松井茂>
松井 茂(まつい しげる、1866年11月4日(慶応2年9月27日) - 1945年(昭和20年)9月9日)は、日本の内務官僚、政治家。
1901年から翌年まで欧米各国を巡歴し警察及び消防を視察、救助はしご車の輸入や救急自動車の導入に尽力する等、日本に於ける警察と消防行政の基礎を築いた人物である。
松井茂
参考文献:松井茂 『欧米警察見聞録』 1909年 警察協会
西洋に於ては、概して宗教上よりして我邦の如くに二人一所に死することはない、故に我國の如き情死等の類は極めて稀なりとの事である。
松井茂 『欧米警察見聞録』 1909年 警察協会 p.47
ものの道理をよく考えてみると、ある人が、どんな苦難であろうと、また自分の関与しない罪を耐え忍ぶことができずに自分の身を殺したばあい、それを度量が大きいということさえも正しくないであろう。じっさい、自分の身体の苦しい隷属やあるいは大衆の愚かな意見を耐え忍ぶことができないのは、むしろ精神の虚弱と認められるのである。
アウグスティヌス 『神の国1』 1984年 岩波書店 p.71
まして創造主が命令するばあいにはどうであろう。それゆえ、自殺してはならないときかされている人も、その命令を軽んじてはならないものが命ずるばあいには自殺しなければならない。ただ必要なのは、この神の命令が不確実なものによって動かされてはいないかどうかを知ることである。
アウグスティヌス 『神の国1』 1984年 岩波書店 p.80
余の寡聞なる未だ歐米各國に此類多きを耳にせす偶々之れあるも眞に稀有の事にして本邦の如く頻繁ならさるか如し
呉文聡 『統計実話』 1899年 丸善 p.59
近來の新聞紙上、頗る情死多し、
男女の情死は世界に於て殆ど我國の専有物たるが如し、つまらないものを専有物とせる哉、
大正名著文庫 『放言録』 1915年 至誠堂書店 p.109
試に各新聞を執り其第三面を一瞥せよ、殆ど連日若くは隔日に血腥(ちなまぐさ)き記事なきはなく、少くも一週間に兩三回の情死記事なきはなきに非ずや。
塚越芳太郎 『教育叢書』 1902年 民友社 p.108
余か今調査し得たる事実は去る二十八年一月より昨三十一年五月に至る二三の小新聞より採集せしものにして情死の数は都合一百一回とす
呉文聡 『統計実話』 1899年 丸善 p.63
一 佛敎に輪廻應報の説あること
二 主從は一世夫婦は二世親子は一世と云ふ説行はれ夫婦は此世のみの縁にあらす來世も亦夫婦となるへきものなりとの説あること
三 浄瑠璃に情死又は情死に類似せる歌曲多くありて衆民日夜口之を歌ひ耳之を聞くこと
四 演劇に於ても同様なる狂言多きこと
呉文聡 『統計実話』 1899年 丸善 p.60
蓋し情死の我國に多かりしは、佛敎の影響その第一にありて、はかなき現世を悲観すると共に樂しき來世を願ひ、一蓮托生の信念に驅られ夫婦は二世の諺に迷ひ、これに世間の義理柵と情緒纏綿の離れ難きとを加へて死せるものといふべし、
今日の情死は未來夫婦の舊思想よりも、現在に於ける情死者の心理狀態と家庭の生活狀態と社會の境遇上とに最も重き原因ありて、
大正名著文庫 『放言録』 1915年 至誠堂書店 p.113
昔し流行た謠に「情死しましよか髪切ましよか髪ハ生もの身はたから」と云ふ文句が御座ります
此奴は一番むかし風に立戻て髪を切て誓を立た方が極手輕でよい様に思ハれます
痩々亭骨皮道人 『滑稽独演説』 1887年 共隆社 p.126
昔しならば髪を切る處なれども當時ハ髪を切るのも餘り値打がありませんからソコハ臨機應變で何とか新發明の氣證を作り死でも命のある様な工夫をして貰いたいと申すので御座います
痩々亭骨皮道人 『滑稽独演説』 1887年 共隆社 p.131
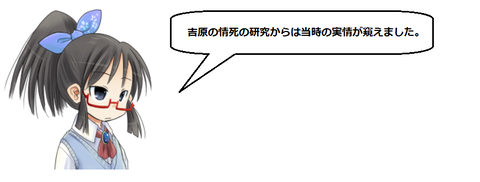
お客の男に迫られて、娼妓も死ぬ氣になつて情死するやうな場合は、斷じて無いと云つて宜い、男から發意した場合のは十中の八九まで無理心中である、大抵の情死は皆娼妓から申込むのである、夫れも惚れ合つた男との眞の情死は、夢にも見る事が出來ぬと云つて宜い、
情死でも爲ようとする娼妓だもの、美人ではない、お客が少ない、借金がある、新造に馬鹿にされる、遣手に叱られる、内所の御機嫌を損ねる、そこで生きて居ても詰らぬと考へる、自殺しやうと覺悟する、然も一人で死ぬのは淋しい、道連が欲しくなる、誰彼の差別はない、男でありさへすれば一所に死なうとする、
吉原に於ける娼妓の情死はこれが眞實である、淺薄な見解だが、事實は案外平凡なものだ、
大道和一 『情死の研究』 1911年 同文館 pp.95-96