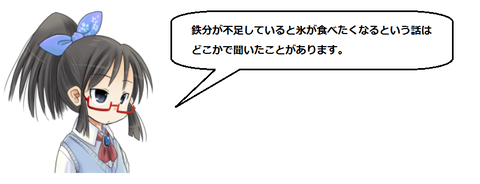スレッド「俺達の自動車を買ってくれ、良い製品だよ」より。
引用:4chan
(海外の反応)
1  万国アノニマスさん
万国アノニマスさん
俺達の自動車を買ってくれ、良い製品だよ
2  万国アノニマスさん
万国アノニマスさん
日本車のほうが上だから
↑  万国アノニマスさん
万国アノニマスさん
本当それ
↑  万国アノニマスさん
万国アノニマスさん
本当それ
↑  万国アノニマスさん
万国アノニマスさん
スレを終わらせるな

Just another WordPress site
こちらは明治時代の社会主義者だった金子喜一が、明治30年代に数年間アメリカ合衆国に滞在して書いた米国案内書(『海外より見たる社会問題』)で、興味深かった記述や当時の社会の様子が窺える記述を取り上げた記事です。関連記事
なお、引用箇所の一部には現代の基準だとあまり良くない表現がある場合もありますが、歴史的記述であることを尊重し一切手を加えていません。
<金子喜一>
1876-1909 明治時代の社会主義者。
明治9年10月21日生まれ。32年渡米してハーバード大にまなび,社会主義に傾倒。日本の「万朝報(よろずちょうほう)」や週刊「平民新聞」などに寄稿。のち「シカゴ-ソーシャリスト-デーリー」の記者となり,社会主義の普及につとめた。42年療養のため帰国。明治42年10月8日死去。34歳。神奈川県出身。著作に「海外より見たる社会問題」。
金子喜一
参考文献:金子喜一 『海外より見たる社会問題』 1907年 平民書房
離婚問題ほど、米國民の頭脳をなやます問題はないであらふ。
佛國の一記者が曾て米國に来て、離婚數(すう)の甚しく多いのを見て、米國は『仁恵の郷土』であると評したが、成るほどキヤソリツク教の如き宗教に依りて支配されてゐる國からみれば、僅かに一種の仁恵に相違あるまい。
一度結婚すれば如何なる事情ありとも離婚のゆるされぬのはキヤソリツク教の信仰であつて、近時に至るまでかかる思想信仰が一般社會(しゃかい)の道義の上に及ぼしたる咸化は、惡しき方にも、又善き方にも非常な者であつた。
金子喜一 『海外より見たる社会問題』 1907年 平民書房 pp.11-12
10:11
そこで、イエスは言われた、「だれでも、自分の妻を出して他の女をめとる者は、その妻に対して姦淫を行うのである。
10:12
また妻が、その夫と別れて他の男にとつぐならば、姦淫を行うのである」。
マルコによる福音書(口語訳)
米國には離婚數が非常に多い、殊に近年はその數を増加しつつあり、此國人の佛蘭西(フランス)に旅行するものの多いのは、彼國は離婚手續(てつづき)が最も簡單なためだといふ人がある、識者はその原因を自由結婚の弊なりといひ、ある人は生活難のためだといひ、又ある人は文化爛熟の結果だといふが、私は女尊男卑が最大の原因だといひたい、
村上巧児 『亜米利加みやげ』 1930年 村上巧児 p.150
我往古ノ法律ニ於テ決シテ離婚ヲ許ササリシ所以ハ當時舊敎ノミ獨リ法律ノ認可スル所ナルヲ以テ大ニ其威權ヲ逞フシ漸ク民事上ノ制規ニ干渉シテ遂ニ婚姻ヲ解クヘカラサルノ主義ヲシテ世ニ行ハレシムルニ至レルニ在リトス
ムールロン 『仏蘭西民法覆義 第4巻』 1881年 司法省 p.102
古法我古法ハ離婚ヲ許ササリシ離婚ハ「カトリツク」教ノ禁スル所ナリ而シテ此時代ニ在テハ宗法ノ命令ハ立法者ニマデ及ヒタリ
ラカンチヌリ 『仏国民法正解 人事編 中巻』 1890年 司法省 p.337
舊敎信者二在テ若シ離婚スル時ハ其宗規ニ反スルノ恐レアレハ乃チ分居ノ制ニ依頼セシメ又他宗ニシテ更ニ宗規ニ管セサル者ノ如キハ直チニ離婚スルヲ得セシメタルモノナリ
ムールロン 『仏蘭西民法覆義 第4巻』 1881年 司法省 p.104
立法者ハ「カトリツク」宗信者ノ心ヲ滿足セシムル爲メ民法中別居ノ制ヲ設クルニ當テ
ラカンチヌリ 『仏国民法正解 人事編 中巻』 1890年 司法省 p.335
Q7:民法上の離婚をしてしまいました。もう教会に行ってはいけないのでしょうか?
まず第一に所属教会の主任司祭に話してください。あなたの主任司祭から結婚問題手続き部門に連絡されます。あなたが民法上離婚したことが直ちに問題になるのではありません。しかし、あなたがこれから信仰生活を歩んでいく上で、ゆるしの秘跡や聖体拝領のことなどで不安や心配を感じないためにも教会法上の別居許可が必要です。しかし、これは再婚の許可ではありません。
特に、再婚の可能性や希望がある場合、前婚(教会で結婚式をしていた場合でも、そうでない場合でも)の絆について教会の審判(前婚の絆の解消手続き、あるいは前婚の無効宣言手続き)が必要となります。民法上の離婚をしたにもかかわらず、教会には何も連絡をせず、再婚を決めてしまってからでは、そのときになって手続きが必要なことに気が付いて困惑してしまうことになりますので、民法上の離婚をした場合は速やかに所属教会の主任司祭にお話しくださるようお願いいたします。
カトリック教会の結婚観 | カトリック東京大司教区 ウェブサイト
養老律令(ようろうりつりょう)は、古代日本で757年(天平宝字元年)に施行された基本法令。構成は、律10巻12編、令10巻30編。大宝律令に続く律令として施行され、古代日本の政治体制を規定する根本法令として機能した。
しかし、平安時代に入ると現実の社会・経済状況と齟齬をきたし始め、平安時代には格式の制定などによってこれを補ってきたが、遅くとも平安中期までにほとんど形骸化した。廃止法令は特に出されず、形式的には明治維新期まで存続した。
養老律令
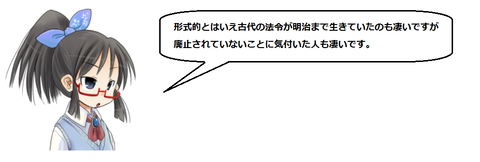
続きを読むスレッド「トトロのバス停を現実で再現した老夫婦」より。宮崎県高原町にある手作りのトトロのレプリカが話題を集めていたので反応をまとめました。
引用:Boredpanda、Facebook、Facebook②
こちらは明治時代の作家だった巖谷小波が、明治42年(1909年)に渋沢栄一を団長とする日本実業家団体の米国視察に同行した時の視察記/旅行記(『新洋行土産』)で、興味深かった記述や当時の社会の様子が窺える記述を取り上げた記事です。関連記事
なお、引用箇所の一部には現代の基準だとあまり良くない表現がある場合もありますが、歴史的記述であることを尊重し一切手を加えていません。
<巖谷小波>
巖谷 小波(いわや さざなみ、1870年7月4日(明治3年6月6日) - 1933年(昭和8年)9月5日)は、明治から大正にかけての作家、児童文学者、口演童話家、俳人、ドイツ文学者、ジャーナリスト。
今日有名な『桃太郎』や『花咲爺』などの民話や英雄譚の多くは彼の手によって再生され、幼い読者の手に届いたもので、日本近代児童文学の開拓者というにふさわしい業績といえる。
巖谷小波
参考文献:巌谷小波 『新洋行土産 上巻 』 1910年 博文館
亜米利加人と日本人とは、朝から氷水を飲む国民と、朝から味噌汁を吸はねば心持の悪い国民との相違がある。
巌谷小波 『新洋行土産 上巻 』 1910年 博文館 p.334
佛蘭西人が葡萄酒を飲み、獨逸人が麦酒を傾ける代りに、亞米利加人はただの氷水を飲む。関連記事
杉村楚人冠 『半球周遊』 1909年 有楽社 p.29
米人は氷を用ること甚だ多く家々皆其供給者と約束して毎朝若干斤を配達せしむ旅館、停車場、滊車内等に於て一般の用に備ふる飲用水も皆氷塊を投入したる所所謂る氷水なり、われ等も米国旅行中は平均一日に六七杯の氷水を飲まざる日なかりき関連記事
正木照蔵 『漫遊雑録』 1901年 正木照蔵 pp.159-160
米國に入ってから米人の氷水を多量に絕ゑず用うるのには、如何にも驚いた。
ここは加奈太である。日本の千島、占守島あたりと略同緯度の所だといふ。それだのに、毎朝食卓に就くと、第一に氷水を持ってくる。
僕は、飲まないけれど、他の人はガブガブ飲んで居る。製氷事業が、米國に於て(加奈太にかけ)大なる事業の一つである。從つて氷價も亦廉い、配達して一斤一銭といふ所もあり、五厘といふ所もあり、三厘にしか當らないといふ所もあつた。
之を飲めば、衛生上にも益ありと、醫師から勸めて居る所もあるらしい。
田川大吉郎 『欧米都市とびとび遊記』 1914年 二松堂書店 p.295
米國人は生水を平氣で飲む。生水は健康だと云つて、寧ろ迷信的に飲む。彼等は牛乳よりも新らしい生の水が有効だと心得てゐる。日本人が決して生水をのまぬといふことを不思議がつてる。
米國人は日本人が生水を呑まぬ如くに、白湯は決してのまぬ。
彼等は氷をのむのを恐れぬ。生水の中に氷の小片を浮べて、水の極めて冷やかなるを酷愛する。寒中と雖も然りだ。
田村松魚 『北米世俗観』 1909年 博文館 pp.88-89
生水を飲むことは、ちょうど生のキャベツをかじるのと同じで、乞食さえ思いつかぬことであろう。
オイレンブルク 『オイレンブルク日本遠征記 上』 1969年 雄松堂書店 p.263