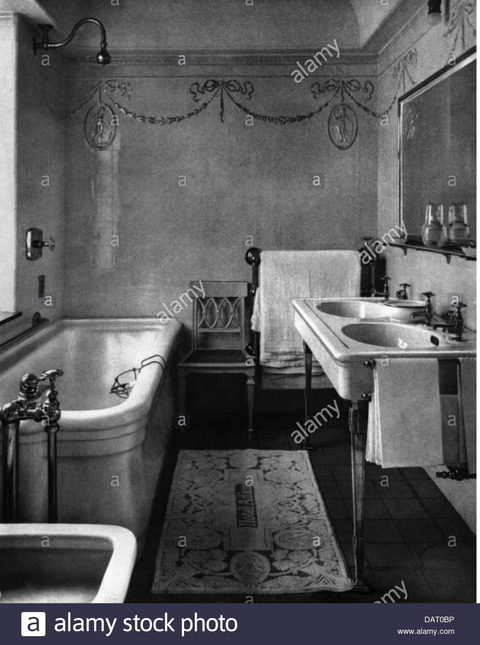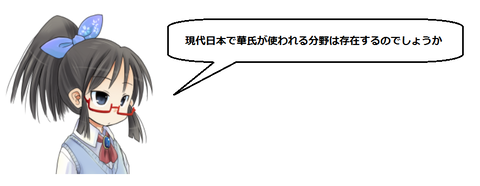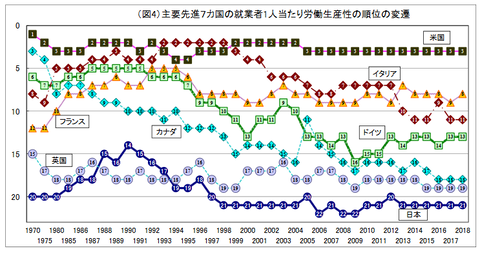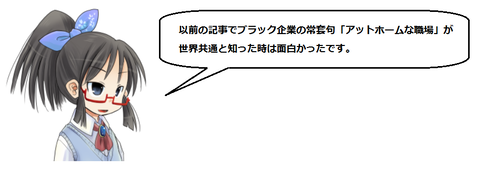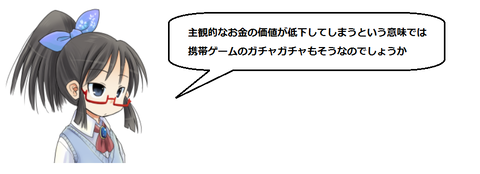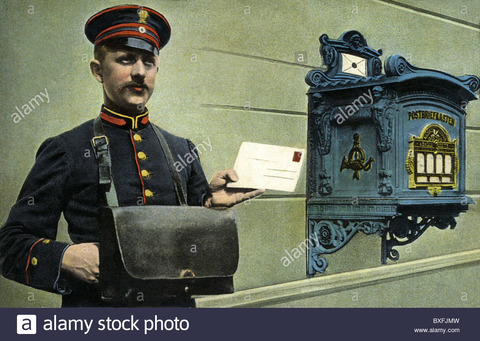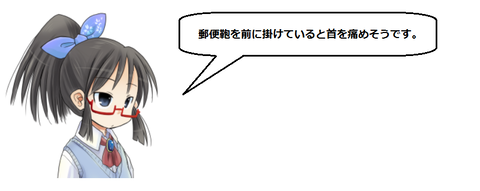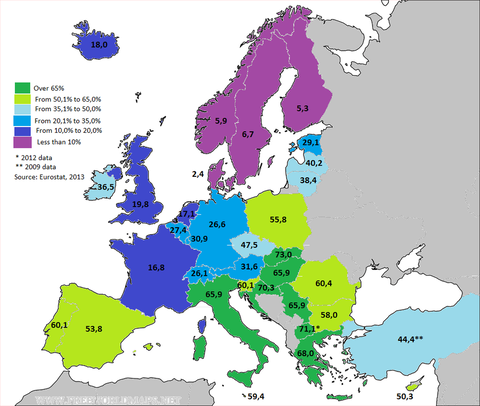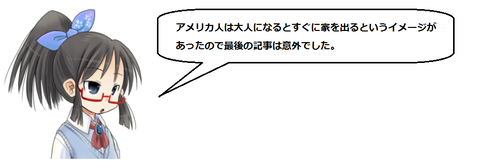こちらは大正時代の新聞記者だった高原操が、大正11年(1922年)に欧米各国の新聞会社を見聞した時の旅行記(『欧米新聞遍路』)で、興味深かった記述や当時の社会の様子が窺える記述を取り上げた記事です。関連記事
なお、引用箇所の一部には現代の基準だとあまり良くない表現がある場合もありますが、歴史的記述であることを尊重し一切手を加えていません。
<原田譲二>
原田 譲二(はらだ じょうじ、1885年3月26日 - 1964年2月10日)は、日本のジャーナリスト。貴族院勅選議員。
1907年早稲田大学卒。報知新聞社に入り、1915年、東京朝日新聞社に入る。社会部長を経て、1925年、大阪朝日新聞社に入る。同社では編集局長から専務となり、1946年8月14日、貴族院勅選議員となった。
原田譲二
参考文献:原田譲二 『欧米新聞遍路』 1926年 日本評論社
【宣伝】暇劇の同人誌(『幕末・明治期の西洋人が見た日本(絵画篇)』)が完成しました。
【宣伝】暇劇の同人誌第二弾(『幕末・明治期の西洋人が見た日本(入浴文化篇)』)が完成しました。
[PR] 暇は無味無臭の劇薬のYouTubeチャンネル
●こちらは日本人が外国へ行くと偉人の墓をよく訪れることについての記述です。
日本人には展墓癖といふやうなものがあつて、外國へ來ると、よく偉人の墓を弔ふ。
紐育から連れて来た運轉手は、勿論彼等の偉大な大統領が、どこに眠つてゐるかを知らない。海に臨んだ小さな町の住民もあまり問題にはしてゐないらしく、尋ね尋ねて、やつと丘の上に辿りついた。
その國の國民さへもが忘れて顧みないのに、わざわざ日本の一無名氏が、遠路自動車を飛ばして参詣する。地下のローズヴェルトも合點が行くまいが、土地の人は猶更不思議に思つたであらう。
過去を懐かしむ心、故人を追慕する情、かういふものは日本人の特質と思はれる。
原田譲二 『欧米新聞遍路』 1926年 日本評論社 p.96
【要約】
日本人が外国へ行くとよく歴史上の人物の墓を訪れる癖があり、自身も地元の人ですらよく分かっていないセオドア・ルーズベルトの墓を訪れたという内容です。原田譲二はこの点を以て日本人には過去を懐かしむ特質があるとしています。
※セオドア・ルーズベルトの墓

【備考】
明治時代の旅行記を読んでいるとよく歴史上の人物の墓参りをしているのですが、特にその事に今まで注意を払っていなかったので上記のような指摘は目から鱗でした。
訪れている墓は様々ですが、その中でもワシントンとペリー提督の墓地を訪れているのが他と比べるとやや多いです。
印象に残っているのが渋沢栄一を代表とする渡米実業団がペリー提督の墓を訪れた時の記述で、内容としては特に目立って何かがあるというわけではありませんが、当時の日本人のペリー提督に対するイメージが集約されているような感じがして記憶に残っています。
此日の墓参は、敢て弔魂の爲めでは無く、むしろ謝恩と云ふべきであらう。五十餘年前の開國の恩人に、平和の大使を以て任ずる、渡米實業團の團長が、特に一日を割いて墓参をするのは、元より當然の、而も大切な事である。
巌谷小波 『新洋行土産 上巻 』 1910年 博文館 p.144
※ペリー提督の墓

墓参りの話題は結構多いため日本と外国の墓地の違いについても言及していることが多く、なかなか興味深いものもあります。
その中でもウェストミンスター寺院を訪れた日本人は、建物の構築上墓を踏まなくてはならないことに言及していることは多く、大抵はその事を嫌がっていて日本人と外国人では墓に対する考え方が違っているという感想を残していることが多いです。
中には靴ぐち踏むでも構はぬ床下の墓もある。日本人の考へから云ふと、甚だ奇異に咸ずるが、歩いて通ほらねばならぬ所にあるから仕方ない。其處は自由の國で、形式を尚ぶ東洋人の考へ及ぶ所でない。
總じて西洋の墓は彫刻的であって、咸情に訴へるのか主になって居る。
田辺英次郎 『世界一周記』 1910年 梁江堂 p.148
予は其英姿を仰いでゐる中に、脚下を見れば、圖(はか)らざりき、大老爺夫妻の墓碑の上に立つてゐるのを見て愕然として去つた。
されど偉人英雄の墓を踏むの無禮を爲(せ)じとならば、此の寺院に入(い)ることは出來ぬ。
桜井鴎村 『欧洲見物』 1909年 丁未出版社 pp.112-113
このことは現代日本人の多くも共感することではないでしょうか。実際ウェストミンスター寺院を訪れた人のブログなどをいくつかググって読んでみましたが、お墓を踏むことに抵抗感があったと感想を残している人が目立ちました。
私自身は残念ながらウェストミンスター寺院を訪れた経験はないのですが、偉人の墓かどうかにかかわらず墓を踏むという行為自体に抵抗感があるので、やはり同じような感想を持つのではないかと感じました。
ウェストミンスター寺院を訪れた外国人のブログもいくつか読んでみたのですが、インド人の方のブログでもウェストミンスター寺院で墓を平然と踏んでいる人たちに愕然とし、自身も通るために墓を踏まざるを得なかったことに抵抗感を覚えたと書かれていました。
関連:I was shocked to see graves under my feet
※ウェストミンスター寺院の墓

他にも墓の違いについては当時の日本人によって色々言及されているのですが、1914年発刊の「欧米都市とびとび遊記」の中で墓に刻まれている文言から死生観の違いに触れている記述はとても興味深いものでした。
庭の入口にあるその墓地には、ワシントンがここに休息すと記してある。死んだとは記しては無い。
死に對する咸念に、どうしても多少の差があるやうだ。
田川大吉郎 『欧米都市とびとび遊記』 1914年 二松堂書店 pp.220-221
明治時代に日本を訪れた外国人も、日本の墓や日本人が持っている墓に対する思いについて関心を示している人は多く旅行記などでは触れていることが結構多いです。
よく言われているのが日本人は墓を大切にするということで、イザベラ・バードは旅行記の中で日本人の良い所として墓を大切にすることを挙げていますが大抵の外国人は同様のことを述べています。
日本人の性格には二つの評価できる特質がある。一つは死者に対して敬意を払うことであり、いま一つは墓地を美しく魅力的にするためにあらゆる気配りをすることである。
東京の墓地は美しさの点では京都には勝てないものの、数多くの墓地はいずれも手入れがよく行き届いており、上は将軍たちが「礼を尽くして葬られ」ているしばや上野の壮麗な廟から、下は人夫の遺骨が眠るとても質素な墓に至るまで、死と生という点では何の厳然たる違いもない。
イザベラ・バード 『完訳日本奥地紀行4』 2013年 平凡社 p.32
他にも外国人ならではの視点だと思ったのは、日本人が墓地にする場所は景観が良い所ばかりであるという指摘です。
東洋の大半の墓地がそうであるように、日本人の墓地にも独特の優美で詩的な趣がある。常に変わらず美しい場所にあって、見晴らしの良い丘の斜面の大きな木の陰に集まっている。
アルフレッド・ルサン 『フランス士官の下関海戦記』 1987年 新人物往来社 p.172
われわれは、われらが死者のために、自然のふところに抱かれたかくも壮麗な墓所を選んだことはかつてない。
A・ベルソール 『明治滞在日記』 1989年 新人物往来社 p.12
大抵こういう記述と共に日本人は自然愛好家であると述べられているのが定番なのですが、初めてこういう記述を読んだ時は、あえて意識をせずともなるべく景観が良い所を選ぶというのはどちらかと言えば普通の事ではないかと言う考えだったので、西洋人がそういうことをあまり意識していないということに結構驚いた記憶があります。
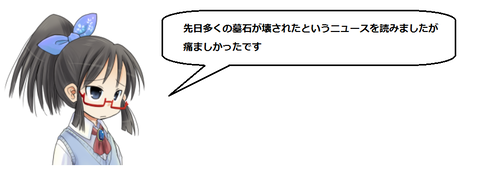
群馬県藤岡市上落合の宗永寺(清章司住職)に隣接する墓地が荒らされ、約70基の墓石が倒されていたことが23日、分かった。複数の墓石が破損したほか、灯籠や地蔵、花立てなどにも被害が及び、群馬県警藤岡署は器物損壊事件として捜査を始めた。市内の別の墓地でも墓石が倒される被害が相次いで確認されており、同署が関連を調べている。
藤岡で墓石倒し 宗永寺で70基 灯籠や地蔵も被害 藤岡署が捜査 市内の他地域でも相次ぎ確認